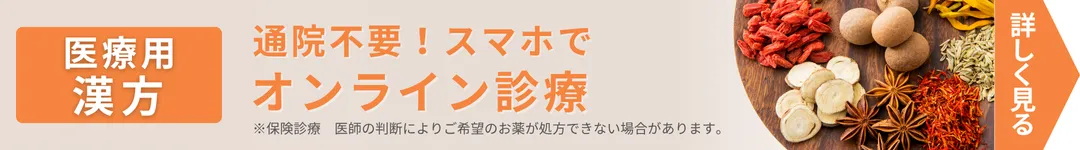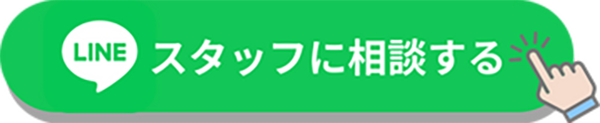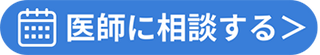漢方と飲み合わせの悪い医薬品は?飲み物や食べ物との相性についても解説
ホーム > ブログ


日本赤十字社医療センター、虎の門病院で産婦人科医として臨床経験を積む。「忙しく頑張っている人がもっと気楽に相談できる場所を作りたい」との想いを胸に、2024年11月、オンライン診療専門のシンクヘルスクリニックを開院。
内科、皮膚科、医療用漢方、婦人科など、受診者の悩みに幅広く対応。心のケアも大切に、一人ひとりが安心して自分の体と向き合えるようサポートしている。
目次
1 漢方薬とほかの薬は併用しても大丈夫?
2 飲み合わせに注意が必要な漢方薬
2.1 葛根湯(かっこんとう)
2.1.1 特徴
2.1.2 副作用
2.1.3 ほかの医薬品との飲み合わせの注意点
2.2 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)
2.2.1 特徴
2.2.2 副作用
2.2.3 ほかの医薬品との飲み合わせの注意点
2.3 麻黄湯(まおうとう)
2.3.1 特徴
2.3.2 副作用
2.3.3 ほかの医薬品との飲み合わせの注意点
2.4 八味地黄丸(はちみじおうがん)
2.4.1 特徴
2.4.2 副作用
2.4.3 ほかの医薬品との飲み合わせの注意点
2.5 麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう)
2.5.1 特徴
2.5.2 副作用
2.5.3 ほかの医薬品との飲み合わせの注意点
2.6 五苓散(ごれいさん)
2.6.1 特徴
2.6.2 副作用
2.6.3 ほかの医薬品との飲み合わせの注意点
3 漢方薬と飲み物・食べ物との飲み合わせについて
3.1 漢方薬と飲み物の飲み合わせの注意点
3.2 漢方薬と食べ物の同時摂取は避ける
4 漢方の飲み合わせに関するよくある質問
4.1 複数の漢方薬を同時に服用しても良い?
4.2 エキス剤の漢方薬を飲みやすくする方法はある?
4.3 漢方薬と抗生物質は併用しても大丈夫?
4.4 漢方服用後に体調が悪くなったときの対処法は?
7 まとめ
漢方薬は、他の薬や飲み物・食べ物との飲み合わせに注意が必要です。
複数の漢方薬を同時に服用することで、本来の効果が得られなかったり、逆に薬効が増強されてしまったりすることがあるためです。
この記事では、漢方薬の飲み合わせについて詳しく解説します。
飲み合わせに注意が必要な漢方薬の特徴や副作用、飲み合わせの注意点などをまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
| 漢方薬と他の薬は併用しても大丈夫?

漢方薬は他の薬との併用療法もありますが、薬物相互作用(複数の薬物の併用によって薬効が減弱または増強されてしまうこと)のリスクがあるため注意が必要です。
漢方薬は一部の生薬を除き、相互作用の発生について十分に把握されていないという現状があります。
しかし近年、小柴胡湯と他の薬剤の併用により、間質性肺炎を発症する可能性や血糖値に影響する可能性が指摘されています。
その他の漢方薬においても、併用による有害事象のリスクが報告されているため注意が必要です。
そのため漢方薬とほかの薬を併用したい場合には、必ず医師に相談するようにしましょう。
| 飲み合わせに注意が必要な漢方薬

飲み合わせに注意が必要な漢方薬として、以下の6つが挙げられます。
葛根湯(かっこんとう)
半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)
麻黄湯(まおうとう)
八味地黄丸(はちみじおうがん)
麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう)
五苓散(ごれいさん)
ここでは、これらの6つの漢方薬について、それぞれの特徴・副作用・ほかの医薬品との飲み合わせに関する注意点を解説します。
関連記事
漢方が合わないときの症状は?副作用が出やすい人の特徴や原因について解説
| 葛根湯(かっこんとう)
葛根湯の特徴・副作用・他の医薬品との飲み合わせの注意点は以下の通りです。
– 特徴
葛根湯(かっこんとう)は、風邪の初期症状や肩こり、筋肉のこわばりなどに用いられる、代表的な漢方薬です。
主な成分には、葛根、麻黄、桂枝、生姜、甘草などが含まれ、発汗作用を促しながら体を温め、免疫力を高める働きを持ちます。
特に、寒気を伴う風邪のひき始めに効果的とされ、早期に服用することで症状の悪化を防ぐことが期待できます。
関連記事
風邪の予防方法や原因を解説~食べ物や飲み物での対策も~
– 副作用
葛根湯は比較的安全な漢方薬とされていますが、副作用が出ることもあります。
特に麻黄に含まれるエフェドリンによる動悸や発汗過多などに注意が必要です。
また甘草が含まれているため、低カリウム血症やむくみ、高血圧のリスクが高まることがあります。
体質によっては胃の不快感や下痢を引き起こす場合もあるため、異常を感じた場合は服用を中止し、医師に相談することが大切です。
– ほかの医薬品との飲み合わせの注意点
葛根湯には麻黄や甘草が含まれているため、一部の薬との併用に注意が必要です。
例えば同じく甘草を含む他の漢方薬と併用すると、偽アルドステロン症のリスクが高まる可能性があります。
偽アルドステロン症とは、カリウムが体から過剰に失われ、血圧上昇やむくみ、筋力低下などが起こる状態です。
また麻黄を含むため、カフェインや気管支拡張剤といった交感神経を刺激する成分との併用で、動悸や血圧上昇が起こることがあるため、高血圧や心疾患のある人は特に注意が必要です。
市販薬や他の漢方薬と併用する場合は、医師や薬剤師に相談のうえ、安全に服用しましょう。
| 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)
半夏厚朴湯の特徴・副作用・ほかの医薬品との飲み合わせの注意点は以下の通りです。
– 特徴
半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)は、のどの違和感や詰まる感じ、不安やストレスによる不調などを改善する漢方薬です。
主な成分には半夏、厚朴、茯苓、生姜、蘇葉などが含まれており、気の巡りを改善し、消化器の働きを整えながらリラックス効果をもたらします。
特に『梅核気(ばいかくき)』と呼ばれる、のどに異物感がある症状に半夏厚朴湯は効果があるとされています。
また神経性胃炎や不安神経症、ストレスによる胃腸の不調にも効果的な漢方薬です。
– 副作用
半夏厚朴湯の副作用として、発疹や発赤、そう痒などの過敏症が現れる場合があります。
またASTやALTなどの上昇といった肝機能異常が認められる場合もあるため、これらの症状が現れたらすぐに服用を中止しましょう。
– ほかの医薬品との飲み合わせの注意点
半夏厚朴湯の医療用添付文書には、飲み合わせに注意が必要な医薬品は特に記載されていません。
しかし漢方薬同士を併用する場合は、生薬の重複によって薬物相互作用が起こるリスクがあります。
他の漢方薬をすでに服用している場合は、念のため医師に相談しておくと安心です。
| 麻黄湯(まおうとう)
麻黄湯の特徴・副作用・ほかの医薬品との飲み合わせの注意点は以下の通りです。
– 特徴
麻黄湯(まおうとう)は、風邪の初期症状やインフルエンザなどに使用される、強力な漢方薬です。
主な成分には麻黄、桂枝、杏仁、甘草が含まれ、発汗作用を促して熱を下げ、咳を鎮める効果があります。
特に悪寒や発熱、頭痛、関節痛などの症状が強く、汗をかいていない状態のときに有効とされます。
また気管支を広げる作用があるため、喘息や気管支炎の治療にも用いられることがある漢方薬です。
– 副作用
麻黄湯の主な副作用として、過敏症(発疹、発赤など)、自律神経系の不調(不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感など)、肝機能異常、食欲不振、悪心・嘔吐、排尿障害などが挙げられます。
そのほかにも重大な副作用として、偽アルドステロン症やミオパチー(筋力低下にかかわる症状が現れる病気)などが起こる可能性もあります。
上記のような副作用が認められた場合は、すぐに服用を中止して医療機関を受診しましょう。
– ほかの医薬品との飲み合わせの注意点
麻黄湯の併用に注意が必要な医薬品として、『葛根湯』や『小青竜湯』などのマオウ含有製剤、エフェドリン類含有製剤、甲状腺製剤、甘草含有製剤などが挙げられます。
特に『芍薬甘草湯』などの甘草含有製剤は偽アルドステロン症のリスクが高くなるため、注意が必要です。
| 八味地黄丸(はちみじおうがん)
八味地黄丸の特徴・副作用・ほかの医薬品との飲み合わせの注意点は以下の通りです。
– 特徴
八味地黄丸(はちみじおうがん)は、加齢や冷えによるさまざまな不調を改善する効果が期待できる漢方薬です。
主に腎臓の機能を補う作用があり、頻尿や排尿困難、むくみ、冷え、腰痛、足のしびれなどの症状に効果があるとされています。
地黄、山茱萸、山薬、沢瀉、茯苓、牡丹皮、桂枝、附子などの生薬が含まれ、特に下半身の冷えや老化に伴う体力の衰えに対して広く用いられます。
– 副作用
八味地黄丸の主な副作用として、過敏症(発疹、発赤など)、肝機能以上、食欲不振、胃部不快感、悪心・嘔吐、腹痛、下痢、便秘、のぼせなどが挙げられます。
暑がりでのぼせが強く、赤ら顔の方、胃腸が弱い方、食欲不振や悪心・嘔吐などの症状がある方は、上記の副作用のリスクが高まるため注意が必要です。
– ほかの医薬品との飲み合わせの注意点
八味地黄丸は附子を含むため、ほかの漢方薬との併用による過剰摂取に注意が必要です。
附子の過剰摂取はのぼせや動悸が強くなることがあるため、併用する際は服用前に医師や薬剤師に相談することが望ましいでしょう。
| 麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう)
麻杏甘石湯の特徴・副作用・ほかの医薬品との飲み合わせの注意点は以下の通りです。
– 特徴
麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう)は、喘息や気管支炎などの呼吸器系の症状に用いられる漢方薬です。
主な成分には麻黄、杏仁、甘草、石膏が含まれ、気管支を広げる作用や炎症を抑える効果があります。
即効性があり、呼吸を楽にする効果が期待できます。
– 副作用
麻杏甘石湯の主な副作用として、自律神経系の症状(不眠や発汗過多、頻脈、動悸など)、消化器系の症状(食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐など)、排尿障害などが挙げられます。
重大な副作用としては偽アルドステロン症やミオパチーが報告されています。
著しく体力の衰えている方や胃腸の虚弱な方、発汗傾向の強い方などは上記の副作用が現れたり症状が悪化したりする恐れがあるため、服用には注意が必要です。
– ほかの医薬品との飲み合わせの注意点
麻杏甘石湯に併用禁忌薬はありませんが、マオウ含有製剤やエフェドリン類含有製剤、甘草含有製剤などとの飲み合わせには注意が必要です。
特に甘草含有製剤は偽アルドステロン症のリスクが高まるため、なるべく避けた方が良いでしょう。
| 五苓散(ごれいさん)
五苓散の特徴・副作用・ほかの医薬品との飲み合わせの注意点は以下の通りです。
– 特徴
五苓散(ごれいさん)は、水分代謝を調整し、むくみや下痢、頭痛、吐き気などを改善する効果が期待できる漢方薬です。
主な成分は沢瀉、茯苓、猪苓、白朮、桂枝で、これらが体内の余分な水分を排出し、適切な水分バランスを保つ働きをします。
特に二日酔いや水分の滞りによるめまい、むくみなどに効果があり、胃腸の不調にも使用されます。
– 副作用
五苓散の主な副作用として、腎機能障害や間質性肺炎、低ナトリウム血症などが報告されています。
特に高カルシウム血症や間質性肺疾患が多く見られます。
– ほかの医薬品との飲み合わせの注意点
五苓散は飲み合わせに注意が必要な医薬品は特に指定されていません。
しかしどんな薬も過剰摂取は逆効果になる恐れがあるため、ほかの漢方薬や薬と併用したい場合は医師に事前に相談しましょう。
| 漢方薬と飲み物・食べ物との飲み合わせについて

漢方薬は医薬品との飲み合わせだけでなく、飲み物や食べ物との同時摂取にも注意が必要です。
– 漢方薬と飲み物の飲み合わせの注意点
漢方薬を服用する際は、飲み物との相性に注意が必要です。
特にカフェインを含むコーヒーや緑茶、紅茶は、漢方薬の成分と反応し、効果を弱めたり、副作用を引き起こす可能性があります。
そのほかに注意が必要な飲み物として牛乳が挙げられます。
牛乳は胃粘膜を保護する作用がある一方で、漢方薬の吸収を妨げることがあるため、服用前後の摂取は避けるのが望ましいです。
基本的に漢方薬は常温の白湯または水で服用するのが理想的です。
– 漢方薬と食べ物の同時摂取は避ける
漢方薬は空腹時に飲むことで効果が高まりやすいため、食事と一緒に摂取することは推奨されません。
食事と一緒に摂取すると、胃腸の内容物により漢方薬の吸収が妨げられ、十分な効果が得られない可能性があります。
漢方薬は食前30分〜1時間前、または食後2時間ほど空けて服用するのが理想的とされています。
| 漢方の飲み合わせに関するよくある質問

漢方薬の飲み合わせに関するよくある質問をまとめました。
・複数の漢方薬を同時に服用しても良い?
・エキス剤の漢方薬を飲みやすくする方法はある?
・漢方薬と抗生物質は併用しても大丈夫?
・漢方薬服用後に体調が悪くなったときの対処法は?
ここでは上記4つの質問についてそれぞれ解説します。
| 複数の漢方薬を同時に服用しても良い?
複数の漢方薬を同時に服用することは可能ですが、組み合わせによっては効果が強くなりすぎたり、副作用が出ることがあります。
医師や薬剤師に相談し、相性の良い漢方薬を選ぶことが大切です。
また服用する時間をずらすことで、負担を軽減できる場合もあります。
| エキス剤の漢方薬を飲みやすくする方法はある?
エキス剤の漢方薬は独特の苦味や風味があり、飲みにくいと感じることがあります。
飲みやすくする方法としては、少量のぬるま湯でよく混ぜて飲む方法が挙げられます。
さらに匂いや味を抑えたい場合は、よく混ぜた後に氷を入れて飲んだり、オブラートを使ってゼリー状にして飲みやすい形に工夫するのも一つの方法です。
ジュースやコーヒーなどで服用すると、成分が変質したり相互作用が起こる可能性があるため、基本的には白湯または水で服用するのが望ましいです。
| 漢方薬と抗生物質は併用しても大丈夫?
漢方薬と抗生物質の併用は基本的に可能ですが、相互作用によって効果が変化する場合があります。
例えば芍薬甘草湯と抗生物質を併用した研究では、漢方薬単独投与時に比べて、最大約22%にまで血中濃度が低下するという変化がみられました。
(参照:「抗生物質併用投与による漢方薬配糖体成分の体内動態変動とその対策」第23回 日本臨床薬理学会年会)
漢方薬と抗生物質を併用する際は、医師や薬剤師に確認することが重要です。
| 漢方薬服用後に体調が悪くなったときの対処法は?
漢方薬を服用した後に体調が悪くなった場合はすぐに服用を中止し、医師に相談しましょう。
漢方薬は体質に合わないと副作用が出ることがあり、例えば過剰な発汗や下痢、動悸、かゆみなどが現れることがあります。
特に長期間服用していて急に体調が悪化した場合は、体質の変化が影響している可能性もあるため、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
| まとめ
漢方薬は種類によっては他の医薬品や漢方薬、飲み物・食べ物との飲み合わせに注意が必要になります。
漢方薬は体質や他の薬との相互作用によって効果や副作用の現れ方が異なるため、服用前に医師や薬剤師に相談することが重要です。
当院では、医療用漢方の処方を行っています。
自宅でオンライン診療を受けられるので、ご検討ください。
参考文献
- 西村 信弘(2005).漢方薬と西洋薬の消化管吸収過程における相互作用に関する研究 125(4). 363-369.
- 牧野 利明 漢方薬と西洋薬の有機アニオントランスポーターを 介する薬物相互作用に関する研究
- 黒河内 彰 (1992).抗精神病薬の副作用としておこる鼻閉に対する葛根湯の有効性について 43(2). 319-324.
- 石岡 忠夫 青井 禮子(1991).葛根湯の抗炎症作用 22(1). 273-274
- 及川 哲郎 他(2008).半夏厚朴湯の使用目標とその臨床効果との関連について-機能性ディスペプシア患者における検討- 59(4) 601-607.
- 小多口 浩 他 (2019).麻黄の副作用とエフェドリンアルカロイド除去麻黄エキス(EFE)の安全性 139(11). 1417-1425.
- 萩田 善一(1995).八味地黄丸効果の薬理遺伝学的研究 12. 1-9.
- 塚田 悦恵, 渋谷 昭子, 前田 幸宏, 市川 理恵, 日紫喜 光良, 根東 義明(2022).高齢男性の突発性難聴における八味地黄丸投与効果の検討 81(1). 39-44.
- 尾崎 哲,下村 泰樹(1993). 八味地黄丸の意欲賦活作用と抗焦燥作用について-相反する向精神作用の五行論による把握 43(3). 429-437.
- 矢野 敏夫 他(1966).抗生物質の副作用に対する五苓散の効果 17(2). 70-76.
- 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 症例一覧
- 宮本信宏 (2022).五苓散を中心とした利水剤による周術期管理へのサポート 56(2). 69-72.
- 本間真(2006).漢方薬の薬物速度論解析 66(1). 44-49.
- 村松 博 他(2003).抗生物質併用投与による漢方薬配糖体成分の体内動態変動とその対策 34(2). 259-260.