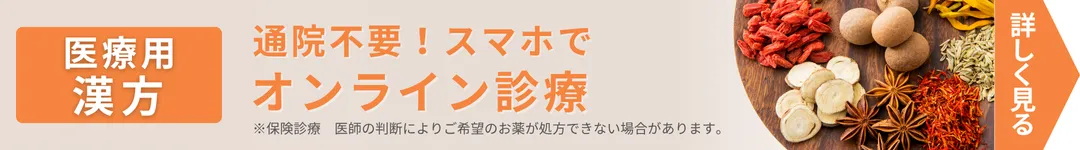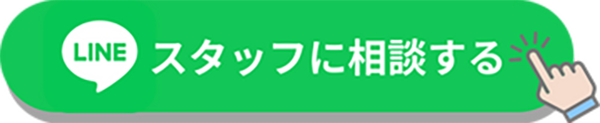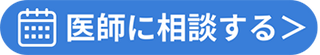漢方が合わないときの症状は?副作用が出やすい人の特徴や原因について解説
ホーム > ブログ


日本赤十字社医療センター、虎の門病院で産婦人科医として臨床経験を積む。「忙しく頑張っている人がもっと気楽に相談できる場所を作りたい」との想いを胸に、2024年11月、オンライン診療専門のシンクヘルスクリニックを開院。
内科、皮膚科、医療用漢方、婦人科など、受診者の悩みに幅広く対応。心のケアも大切に、一人ひとりが安心して自分の体と向き合えるようサポートしている。
目次
1 漢方薬が合わないときに現れる可能性がある症状
1.1 胃もたれ
1.2 食欲不振
1.3 下痢
1.4 膀胱炎
1.5 動悸
1.6 湿疹
1.7 肝機能障害
1.8 間質性肺炎
1.9 偽アルドステロン症
2 漢方薬が合わないときに症状が現れる原因
2.1 複数の漢方薬を服用している
2.2 用法・用量を守らず服用している
2.3 漢方薬が体質に合っていない
2.4 漢方薬の成分にアレルギーがある
3 漢方薬で副作用の症状が出やすい人の特徴
4 副作用の症状が出やすい生薬の例
4.1 麻黄(まおう)
4.2 甘草(かんぞう)
4.3 附子(ぶし)
4.4 大黄(だいおう)
5 漢方薬の副作用を避けるためのポイント
5.1 複数の漢方薬の併用に注意する
5.2 市販薬やサプリメントとの併用に注意する
5.3 漢方薬が合わないときは医師や薬剤師に相談する
5.4 味の感じ方にも注目
6 まとめ
漢方薬は西洋薬と比べて副作用が少ないというメリットがありますが、体質に合わない場合、体調不良を引き起こすこともあります。
具体的に現れる可能性のある症状としては、胃もたれや食欲不振、下痢、膀胱炎、動悸などです。
この記事では、漢方薬が合わないときに現れる可能性がある症状について詳しく解説します。
漢方薬が合わないときに症状が現れる原因や副作用の症状が出やすい生薬の例などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
| 漢方薬が合わないときに現れる可能性がある症状

漢方薬が合わないときに現れる可能性がある症状として、以下が挙げられます。
・食欲不振
・下痢
・膀胱炎
・動悸
・失神
・肝機能障害
・間質性肺炎
・偽アルドステロン症
ここでは、上記の症状についてそれぞれ詳細に解説します。
| 胃もたれ
漢方薬の中には消化器系に負担をかけるものもあり、体質によっては胃もたれが起こることがあります。
特に代謝を促進する漢方は、胃腸が弱い方には刺激が強すぎることがあります。
胃もたれが続く場合は一度服用を中止し、医師に相談しましょう。
関連記事
胃もたれが続く女性の原因や症状を解説~治らないときの対処法も~
| 食欲不振
漢方薬が体に合わない場合、食欲不振になることがあります。
特に胃腸の弱い方はこの副作用のリスクが高まるため、注意が必要です。
食欲不振が続く場合は、服用を一時中止し、医師に相談することを検討しましょう。
| 下痢
漢方薬に含まれる生薬の一種である大黄によって、下痢が引き起こされることがあります。
大黄に含まれるセンノシド類が大腸を刺激するため、これにより下痢や腹痛などが現れることがあるのです。
特に下痢や軟便などの症状がすでにある方が大黄を含む漢方薬を服用すると、さらに症状が悪化する恐れがあるため注意が必要です。
| 膀胱炎
漢方薬の服用によって、頻尿、排尿痛などの膀胱刺激症状が生じることがあります。
膀胱炎が発症するのは、麻黄を含む漢方薬によるものがほとんどです。
『小柴胡湯』や『柴胡桂枝湯』、『柴朴湯』などの漢方薬の添付文書には、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感、膀胱炎の副作用が起こり得ることが記載されています。
(参照:「ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)」一般財団法人日本医薬品情報センター)
| 動悸
漢方薬の生薬の一種である麻黄に含まれるエフェドリン類により、動悸や頻脈、血圧上昇などの症状が現れることがあります。
これはエフェドリン類により、交感神経を刺激する作用が強くなるためです。
これらの症状が現れた場合、医師に相談し、適切な対処をとることが重要です。
| 湿疹
漢方が合わないときに起こり得る症状の一つとして、薬疹が挙げられます。
薬疹は薬が原因で起こる湿疹のことで、漢方薬の中でも麻黄含有処方に多く見られる症状です。
過去に薬により発疹や発赤、かゆみなどを起こしたことがある場合は、この症状が起こりやすい可能性があるため、事前に医師に相談しましょう。
| 肝機能障害
漢方が合わないときの症状として、肝機能障害が現れることがあります。
肝機能障害の主な症状は発熱、かゆみ、発疹、黄疸、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などです。
この症状も『防風通聖散』や『柴苓湯』などの麻黄含有処方に多く見られます。
また小柴胡湯はかつて肝機能改善目的で用いられることもありましたが、重篤な副作用の報告もあるため、使用には医師の慎重な判断が必要です。
| 間質性肺炎
漢方薬の重篤な副作用として、間質性肺炎が起こることがあります。
間質性肺炎の主な症状には、階段を上ったときの息切れや息苦しさ、空咳、発熱が含まれます。
この副作用が現れやすい漢方薬として、『小柴胡湯』や『柴朴湯』、『柴苓湯』が挙げられます。
| 偽アルドステロン症
偽アルドステロン症も漢方薬の重篤な副作用の一つです。
偽アルドステロン症は、アルドステロンが増加していないにもかかわらず、高血圧やむくみ、カリウム喪失などの症状が現れる状態です。
上記のような症状が続くと、筋障害や不整脈、心不全などの命にかかわる症状につながる恐れがあります。
『芍薬甘草湯』や『抑肝散』などの甘草を多く含む漢方薬で注意が必要です。
| 漢方薬が合わないときに症状が現れる原因力
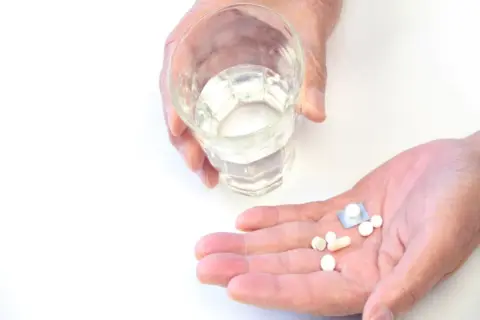
漢方薬が合わないときに症状が現れる原因として、以下の4つが挙げられます。
・用法・用量を守らず服用している
・漢方薬が体質に合っていない
・漢方薬の成分にアレルギーがある
ここでは上記4つの原因についてそれぞれ解説します。
| 複数の漢方薬を服用している
漢方薬によって症状が現れる原因として、複数の漢方薬を服用していることが挙げられます。
複数の漢方薬を併用してしまうと、生薬が重複することがあります。
特に甘草や麻黄、大黄などの症状が現れやすい生薬の重複によって過剰に摂取してしまうと、体調不良を引き起こす可能性があるのです。
| 用法・用量を守らず服用している
漢方薬は用法・用量をきちんと守って服用することが大切です。
用法・用量を守らずに服用してしまうと、本来の効果が得られないだけでなく、体調不良を引き起こす恐れがあります。
また漢方薬は飲めば飲むほど効果が増強されるというわけではありません。
例えば甘草は過剰摂取によって偽アルドステロン症を引き起こすことがありますが、その発症リスクが高まる摂取量が1日2.5g以上とされています。
(参照:「芍薬甘草湯による偽アルドステロン症のため低カリウム血症と横紋筋融解症を来した慢性閉塞性肺疾患の1例」藤原清宏)
このように過剰摂取によって症状が引き起こされる場合があるため、必ず用法・用量を守って服用しましょう。
| 漢方薬が体質に合っていない
漢方薬によって体調不良になる場合、そもそも体質に合っていない可能性が考えられます。
漢方薬は病気の状態や患者さんの体質に合わせて処方するものです。
例えば胃腸が弱い患者さんに胃腸に負担のかかる漢方薬を処方してしまうと、副作用が出やすくなってしまいます。
自分の体質に合った漢方薬を処方してもらうことが大切です。
| 漢方薬の成分にアレルギーがある
漢方薬の服用によって症状が現れる場合、含まれる成分にアレルギーがある可能性が考えられます。
薬が原因で起こるアレルギーを『薬物アレルギー』といい、体の過剰な免疫反応によってさまざまな症状が現れます。
アレルギー反応の中でもよく見られるのが、皮疹やかゆみなどの皮膚症状です。
アレルギーがある場合、重篤な症状である『アナフィラキシー性ショック』が起こる恐れもあるため注意が必要です。
皮膚症状のほか、胃痛や吐き気、視覚異常、息苦しさなどの症状が現れたらすぐに医療機関を受診しましょう。
| 漢方薬で副作用の症状が出やすい人の特徴

漢方薬で副作用の症状が出やすい人の特徴として、以下が挙げられます。
・アレルギーのある方
・高齢者の方
・妊娠中の方
・漢方薬で副作用が現れた経験のある方
上記に当てはまる場合、胃腸の症状やアレルギー反応などが起こりやすいため、事前に医師に相談しましょう。
| 副作用の症状が出やすい生薬の例

漢方薬にはさまざまな生薬が使われていますが、その中でも特に副作用の症状が出やすい生薬として、以下が挙げられます。
・麻黄(まおう)
・甘草(かんぞう)
・附子(ぶし)
・大黄(だいおう)
ここでは上記4つの生薬についてそれぞれ解説します。
| 麻黄(まおう)
麻黄に含まれるエフェドリン類は、頻脈や動悸、血圧上昇、発汗過多、排尿障害などの症状を引き起こすことがあります。
麻黄に含まれるエフェドリン類によって交感神経が刺激されるため、麻黄含有製剤やエフェドリン類含有製剤、モノアミン酸化酵素阻害剤、甲状腺製剤との併用には特に注意が必要です。
また上記の症状のほか、不眠や全身の脱力感などが現れる場合もあります。
| 甘草(かんぞう)
甘草にはグリチルリチンという成分が含まれており、これにより偽アルドステロン症を引き起こすことがあります。
具体的な症状は浮腫、高血圧、低カリウム血症などで、これらの症状が続くことで筋障害や不整脈、心不全などが生じることがあるため注意が必要です。
さらに甘草は1日2.5g以上摂取すると、上記のような症状が悪化する恐れがあります。
眼像含有製剤やグリチルリチン酸およびその塩類を含有する製剤、ループ系利尿剤などが併用注意薬として挙げられています。
| 附子(ぶし)
附子にはアコニチン類が含まれており、この成分によって神経麻痺症状が起こることがあります。
いわゆる附子中毒と呼ばれるもので、主な症状として舌や口のしびれ、めまい、熱管、悪寒などが挙げられます。
ほかの生薬と比べると副作用報告はあまり多くありませんが、摂取量が多いと副作用が生じやすくなるため注意が必要です。
| 大黄(だいおう)
大黄にはセンノシド類が含まれており、この成分によって下痢が起こることがあります。
センノシド類は大腸を刺激する成分のため、胃腸が弱い方が摂取すると副作用が起こりやすくなります。
特に下痢や軟便などの症状がある方は、大黄を含む漢方薬の服用に注意が必要です。
| 漢方薬の副作用を避けるためのポイント

漢方薬の副作用を避けるためのポイントは以下の通りです。
・市販薬やサプリメントとの併用に注意する
・漢方薬が合わないときは医師や薬剤師に相談する
・味の感じ方にも注目する
ここでは上記4つのポイントについてそれぞれ解説します。
| 複数の漢方薬の併用に注意する
漢方薬の副作用を避けるためには、複数の漢方薬の併用に注意することが大切です。
異なる漢方薬を同時に服用した際に、配合されている生薬が重複すると、副作用のリスクが高まることがあります。
例えば甘草を含む漢方薬を複数併用すると、『偽アルドステロン症』の発症リスクが高まります。
漢方薬を併用する際は必ず医師や薬剤師に相談し、安全に服用できるか確認しましょう。
関連記事
オンライン診療で漢方を活用〜自宅で始める体調を整える方法を紹介〜
| 市販薬やサプリメントとの併用に注意する
漢方薬を市販薬やサプリメントと併用すると、予期せぬ副作用が生じることがあります。
サプリメントに使用される成分と漢方薬に含まれる成分が同一のものでも、記載されている名前が異なるケースもあるため注意が必要です。
特にビタミンやミネラルを多く含むサプリメントは、漢方薬の効果に影響を与えることがあるため、服用する前に医師に相談しましょう。
| 漢方薬が合わないときは医師や薬剤師に相談する
漢方薬を服用して体調が悪くなった場合は、すぐに服用を中止し、医師や薬剤師に相談することが大切です。
例えば胃もたれや食欲不振、下痢、湿疹などの症状が現れた場合、漢方薬が体に合っていない可能性があります。
また数日間服用しても症状が改善しない場合は、処方の見直しが必要かもしれません。
漢方は体質に合わせた選び方が重要であり、自己判断で続けると症状が悪化することもあるため、早めに医師に相談することが大切です。
| 味の感じ方にも注目
『良薬口に苦し』という言葉が一般的ですが、漢方では『良薬口にうまし』といわれることがあります。
漢方は苦くて飲みにくいというイメージを持つ方も多いかもしれませんが、実際は自分の体に合っている漢方薬ほど美味しく感じられる場合が多いのです。
味が良ければ絶対に合っているとはいいきれませんが、漢方薬が自分に合っているかどうか自己判断するための指標にはなります。
漢方薬の中には苦みの強いものもありますが、「嫌な苦さではない」と感じられれば、自分の体に合っている可能性が高いです。
| まとめ
漢方が体に合わないときの症状として、胃もたれや食欲不振、下痢、膀胱炎、動悸、湿疹などが挙げられます。
まれに重篤な副作用として肝機能障害や間質性肺炎、偽アルドステロン症などが起こる場合もあるため、少しでも体に合わないと感じたら医師に相談することが大切です。
麻黄や甘草、附子、大黄などの生薬は、特に副作用が現れやすいため注意しましょう。
当院では、オンライン診療による漢方処方を行っています。
患者さん一人ひとりの体質に合った漢方を処方しているため、漢方を試してみたいという方もぜひお気軽にご相談ください。