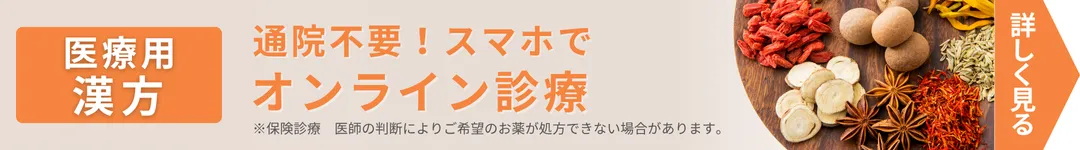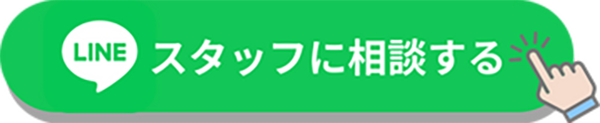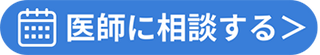漢方で体質改善!気血水の乱れにより起こる症状と体質に適した医療用漢方薬を解説
ホーム > ブログ


日本赤十字社医療センター、虎の門病院で産婦人科医として臨床経験を積む。「忙しく頑張っている人がもっと気楽に相談できる場所を作りたい」との想いを胸に、2024年11月、オンライン診療専門のシンクヘルスクリニックを開院。
内科、皮膚科、医療用漢方、婦人科など、受診者の悩みに幅広く対応。心のケアも大切に、一人ひとりが安心して自分の体と向き合えるようサポートしている。
目次
1 漢方での体質改善に欠かせない気・血・水の基礎知識
1.1 気とは
1.2 血とは
1.3 水とは
2 気・血・水で現在の体の状態を判断できる
2.1 気の乱れにより起こる症状
2.1.1 気虚(ききょ)
2.1.2 気鬱(きうつ)
2.1.3 気逆(きぎゃく)
2.2 血の乱れにより起こる症状
2.2.1 血虚(けっきょ)
2.2.2 瘀血(おけつ)
2.3 水の乱れにより起こる症状
2.3.1 水毒(すいどく)
3 漢方における体質の考え方
3.1 実証
3.2 虚証
3.3 中間証
4 体質改善が可能な医療用漢方薬の種類
4.1 加味逍遙散(かみしょうようさん)
4.2 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
4.3 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
4.4 五苓散(ごれいさん)
4.5 葛根湯(かっこんとう)
4.6 防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)
4.7 芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)
5 まとめ
現代社会では、ストレスや不規則な生活習慣によって体調を崩す方が増加しています。
漢方医学では、体の不調は『気・血・水(き・けつ・すい)』のバランスが崩れることによって起こると考えられています。
漢方はこれらのバランスを整えることで、体質改善を目指すことが可能です。
この記事では、体質改善に適した医療用漢方薬について解説します。
漢方における気・血・水の基礎知識や体質の考え方などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
| 漢方での体質改善に欠かせない気・血・水の基礎知識

漢方での体質改善には、『気・血・水(き・けつ・すい)』の基礎知識の理解が欠かせません。
これは漢方医学(東洋医学)の理論に基づく体質診断の方法であり、現代医学とは異なる視点で全身状態を捉えるものです。
これら3つがバランスよく巡ることで、私たちの健康が維持されているというのが、漢方医学の基本的な考え方です。
ここでは気・血・水それぞれがどのような概念なのか解説します。
| 気とは
『気』は生命を維持するためのエネルギーのようなもので、体のあらゆる機能を支えています。
気は食事や呼吸などにより作られ、全身をめぐることにより内臓の働きを活発にし、血液や水分の流れを調整しているのです。
気のバランスが崩れると、『気虚(ききょ)』や『気鬱(きうつ)』といった不調が現れます。
気虚はエネルギー不足の状態で、疲れやすさ、息切れ、食欲不振、免疫力の低下などが見られます。
一方、気鬱は気の巡りが滞る状態で、気が喉の部分にとどまって咳が出たり、お腹にたまって腫れたりする症状を引き起こすものです。
| 血とは
『血』は全身に酸素や栄養を運び、体を温め、内臓や皮膚、髪の健康を維持する役割を果たしています。
また精神の安定にも関わっており、血の状態が悪くなると不眠やイライラの原因にもなります。
血の乱れには、主に『血虚(けっきょ)』と『瘀血(おけつ)』の2つのタイプがあります。
血虚は血が衰えた状態で、集中力の低下、不眠、めまい、過少月経、抜け毛などの症状が見られます。
一方、瘀血は血の巡りが悪く滞っている状態で、目の周りのクマや不眠、精神症状、腰痛などの症状を引き起こします。
気と血はセットで考えられ、血が器で、その中身に当たるものが気です。
気血は加齢や病気により減少すると考えられています。
| 水とは
『水』は体内の水分やリンパ液、消化液などを指し、体を潤し、老廃物の排出を助ける重要な役割を担っています。
水分が適切に巡ることで、関節の動きがスムーズになり、皮膚の潤いが保たれ、消化吸収もスムーズに行われます。
しかし、水分バランスが崩れると『水毒(すいどく)』と呼ばれる不調が起こるため注意が必要です。
水毒の症状にはむくみや冷え、関節の痛み、胃腸の不調、めまい、鼻炎などが含まれます。
特に体の水分代謝が悪い人は、湿気の多い季節や雨の日に体調を崩しやすい傾向があります。
| 気・血・水で現在の体の状態を判断できる

気・血・水で現在の体の状態を判断することが可能です。
3つのバランスが一つでも崩れると、以下のような症状が現れることがあります。
| 体の状態 | 身体症状 | |
| 気の乱れにより起こる症状 | 気虚 (ききょ) |
体がだるい、気力がない、疲れやすい、日中の眠気、食欲不振、風邪をひきやすい、物事に驚きやすい、下痢など |
| 気鬱 (きうつ) |
抑うつ傾向、頭が重い、喉のつかえ感、胸の詰まった感じ、腹部膨満感、朝起きにくく調子が出ない、排ガスが多い、げっぷ、残尿感、腹部の鼓音など | |
| 気逆 (きぎゃく) |
冷えのぼせ、動悸発作、発作性の頭痛、嘔吐、腹部発作、物事に驚きやすい、焦燥感、顔面紅潮、下肢・四肢の冷えなど | |
| 血の乱れにより起こる症状 | 血虚 (けっきょ) |
集中力低下、不眠・睡眠障害、眼精疲労、めまい、こむらがえり、過少月経、月経不順、顔色不良、抜け毛、爪の異常、知覚障害など |
| 瘀血 (おけつ) |
まぶたの色素沈着、顔面の色素沈着、口唇・歯肉・舌の暗赤化、月経障害など | |
| 水の乱れにより起こる症状 | 水毒 (すいどく) |
体が重い、拍動性の頭痛、頭が重い、車酔いしやすい、めまい、立ち眩み、悪心・嘔吐、朝のこわばり、浮腫など |
ここでは上記の症状についてそれぞれ解説します。
| 気の乱れにより起こる症状
気の乱れが引き起こす症状として、以下の3つが挙げられます。
・気虚(ききょ):気が不足した状態
・気鬱(きうつ):気の流れが滞っている状態
・気逆(きぎゃく):気が下から上に逆流した状態
それぞれの症状について見てみましょう。
– 気虚(ききょ)
気虚(ききょ)は気の不足により起こる状態で、主に以下のような身体症状が現れます。
・体がだるい
・気力がない
・疲れやすい
・日中の眠気
・食欲不振
・風邪をひきやすい
・物事に驚きやすい
・下痢など
気力がなくなったり疲れやすくなったりするのが主な症状で、下痢や食欲不振などを引き起こす場合もあります。
– 気鬱(きうつ)
気鬱(きうつ)は気の流れが滞った状態で、主に以下のような身体症状が現れます。
・抑うつ傾向
・頭が重い
・喉のつかえ感
・胸の詰まった感じ
・腹部膨満感
・朝起きにくく調子が出ない
・排ガスが多い
・げっぷ
・残尿感
・腹部の鼓音など
抑うつ傾向というのは、気分が落ち込み憂うつな状態が続くことです。
気の流れが滞ることにより、上記のように体にさまざまな不調が現れます。
– 気逆(きぎゃく)
気逆(きぎゃく)は気が下から上に逆流した状態で、主に以下のような身体症状が現れます。
・冷えのぼせ
・動悸発作
・発作性の頭痛
・嘔吐
・腹部発作
・物事に驚きやすい
・焦燥感
・顔面紅潮
・下肢・四肢の冷えなど
気がゆっくりと上に上がってくると『のぼせ』となり、足が冷えて顔が熱く感じられることがあります。
逆に気が急に激しく上ると、動悸発作や発作性の頭痛などの症状が現れます。
| 血の乱れにより起こる症状
血の乱れにより起こる症状は以下の2つが挙げられます。
・血虚(けっきょ):血が衰えた状態
・瘀血(おけつ):血の巡りが悪く滞っている状態
それぞれの症状について見てみましょう。
– 血虚(けっきょ)
血虚(けっきょ)は血が衰えた状態で、主な症状は以下の通りです。
・集中力低下
・不眠・睡眠障害
・眼精疲労
・めまい
・こむらがえり
・過少月経
・月経不順
・顔色不良
・抜け毛
・爪の異常
・知覚障害など
血虚は上記のようにさまざまな症状を引き起こし、日常生活にも影響を与えることがあります。
– 瘀血(おけつ)
瘀血(おけつ)は血の巡りが悪く滞っている状態で、以下のような身体症状が現れます。
・まぶたの色素沈着
・顔面の色素沈着
・口唇・歯肉・舌の暗赤化
・月経障害など
上記のように、血の巡りが悪くなると色素沈着や顔色の悪化などの症状を引き起こします。
また血虚や瘀血などは局所的な血流の低下が伴うことが多く、冷えやのぼせなどの症状がみられる場合もあります。
| 水の乱れにより起こる
水の乱れにより起こる症状は『水毒(すいどく)』または『水滞(すいたい)』と呼ばれます。
– 水毒(すいどく)
水毒(すいどく)は水の流れが滞った状態で、主に以下のような症状がみられます。
・体が重い
・拍動性の頭痛
・頭が重い
・車酔いしやすい
・めまい
・立ち眩み
・悪心・嘔吐
・朝のこわばり
・浮腫など
子どもの場合は喉の渇きや嘔吐、下痢、むくみ、尿量の減少といった症状が現れることもあります。
| 漢方における体質の考え方
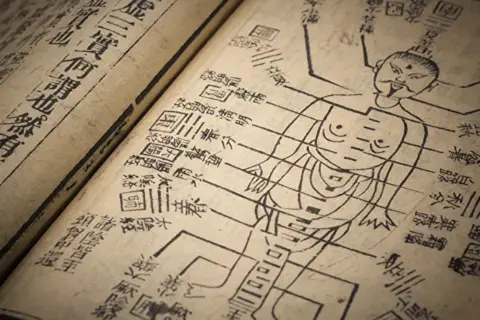
漢方における体質の考え方には3つの分類があります。
・実証:エネルギーが過剰で体力があるタイプ
・虚証:エネルギー不足により体力が少ないタイプ
・中間証:その中間に位置するタイプ
漢方で体質改善を目指すのなら、これらの考え方を理解しておくことが大切です。
ここでは上記3つの分類についてそれぞれ解説します。
| 実証
実証はエネルギーや体力が豊富で、疲れにくいタイプを指します。
このタイプは新陳代謝が活発で、病気になっても回復が早い傾向があります。
ただしエネルギーが過剰なため、不要な毒素を体にため込みやすく、さまざまな症状を引き起こしやすい点が特徴です。
| 虚証
虚証はエネルギーや体力が不足しがちなタイプで、疲れやすく、冷えやすい傾向があります。
体が細く顔色が青白いことが多く、食が細かったり胃腸が弱かったりする人も多いです。
また免疫力が低いため、風邪をひきやすい、貧血気味、立ちくらみをしやすいなどの症状が見られることがあります。
| 中間証
中間証は実証と虚証の中間に位置するタイプで、比較的バランスの取れた体質を持っています。
しかし環境の変化やストレス、生活習慣によって実証寄りにも虚証寄りにもなりやすく、その時々の体調に合わせたケアが必要です。
例えば疲れが溜まると虚証のような冷えや倦怠感が出ることもあれば、ストレスが強くなると実証のようにイライラや頭痛を感じることもあります。
| 体質改善が可能な医療用漢方薬の種類

体質改善が可能な医療用漢方薬の種類として、以下が挙げられます。
・加味逍遙散(かみしょうようさん)
・当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
・桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
・五苓散(ごれいさん)
・葛根湯(かっこんとう)
・防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)
・芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)
各漢方薬の特徴を詳しく解説します。
関連記事
漢方と飲み合わせの悪い医薬品は?飲み物や食べ物との相性についても解説
| 加味逍遙散(かみしょうようさん)
加味逍遥散はイライラや不眠、冷え性などの原因がはっきりしない症状に適した漢方薬です。
女性特有の症状や心身の不調の改善に効果的で、のぼせ感や肩こり、虚弱体質、月経不順などに悩んでいる方に適しています。
| 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
当帰芍薬散は生理不順やめまい、頭痛、貧血、むくみなどの症状に適した漢方薬です。
血の不足を補いながら水の滞りを解消する働きがあり、月経不順や月経困難、不妊症などの症状にも効果が期待できます。
婦人科でもよく処方される漢方薬の一つです
| 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
桂枝茯苓丸は体の血流のバランスを整えたり、痛みを鎮めたりする漢方薬です。
これらの効果によって、生理痛や冷え・のぼせ、肩こり、しみ、更年期障害などの症状の緩和が期待できます。
主に水の停滞を改善し、血の巡りをスムーズにする効果が期待できます。
| 五苓散(ごれいさん)
五苓散は頭痛や水様性の下痢、二日酔いなどの症状に適した漢方薬です。
体内の水分代謝異常を調整する効果があり、浮腫状態では利尿作用、脱水状態では抗利尿作用が期待できます。
むくみや気圧の変化に適しており、水毒により起こる症状にも効果があるとされています。
| 葛根湯(かっこんとう)
葛根湯はかぜの初期症状や肩こりなどに適した漢方薬です。
流行病の急性期症状に対する研究では、葛根湯と小柴胡湯加桔梗石膏の処方により発熱症状が緩和され、呼吸器症状の重症化が抑制されたという報告があります。
(参照:「葛根湯と小柴胡湯加桔梗石膏の併用効果を胸部CTで確認した高齢者COVID-19肺炎の1例」沖本二郎)
服用しても眠くならないため、日中の仕事に影響を出したくない方でも服用できます。
| 防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)
防風通聖散はカンゾウ、マオウ、ダイオウを含む漢方薬で、腹部に皮下脂肪が多く便秘がちな方に適しています。
具体的には高血圧の随伴症状(動悸、肩こり、のぼせ)や肥満症、むくみ、便秘などの改善に効果が期待できます。
胃腸が弱く、下痢しやすい方や虚弱体質の方には、副作用が現れやすいことがあるため、使用は避けた方が良いです。
| 芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)
芍薬甘草湯は就寝中・運動中の足のつりや生理痛、腰痛などの症状に適した漢方薬です。
血の不足を補い、筋肉のけいれんや痛みを和らげる効果が期待できます。
また芍薬甘草湯はさまざまな病気に対する治験が進められており、坐骨神経痛や腎臓結石、筋肉リウマチなどへの効果も示唆されています。
関連記事
漢方が合わないときの症状は?副作用が出やすい人の特徴や原因について解説
| まとめ
漢方には気・血・水という概念があり、これらのバランスが崩れると体調不良を引き起こします。
漢方薬により気・血・水のバランスを改善することで、気の乱れや血の乱れなどにより起こるさまざまな症状を緩和することが可能です。
漢方薬は自分の体質や症状に合ったものを服用することが大切です。
当院では、さまざまな体質に対応できる漢方薬を取り扱っています。
患者さん一人ひとりに適した漢方薬を提供可能ですので、お気軽にご相談ください。