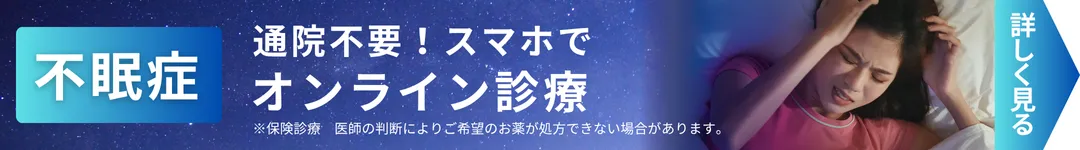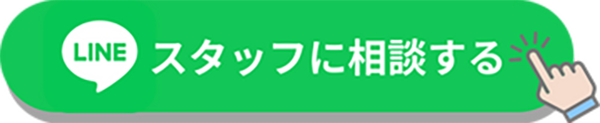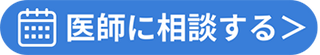寝つきが悪いのはなぜ?~対処法と寝つけないときの過ごし方まで~
ホーム > ブログ


日本赤十字社医療センター、虎の門病院で産婦人科医として臨床経験を積む。「忙しく頑張っている人がもっと気楽に相談できる場所を作りたい」との想いを胸に、2024年11月、オンライン診療専門のシンクヘルスクリニックを開院。
内科、皮膚科、医療用漢方、婦人科など、受診者の悩みに幅広く対応。心のケアも大切に、一人ひとりが安心して自分の体と向き合えるようサポートしている。
目次
1 寝つきが悪い原因
1.1 ストレスを感じている
1.2 睡眠を妨げる行動や習慣
1.2.1 カフェインやアルコールの摂取
1.2.2 入浴時間
1.2.3 就寝前のゲームやスマートフォン
1.2.4 日中の活動
1.3 寝つけないことへの焦り
2 寝つきをよくするための対処法
2.1ストレスへの対処
2.2 睡眠を妨げる習慣の改善
2.2.1 寝る前のカフェインやアルコールを避ける
2.2.2 入浴時間
2.2.3 就寝前のゲームやスマートフォン
2.2.4 日中の活動
2.3 眠らなければと考えすぎない
3 寝つけないときはどうしたらいいのか
3.1 寝床から出る
3.2 考え事への対策
3.3 しないほうがいいこと
4 寝つきの悪さは治療できる?
4.1 不眠症とは
4.2 医療機関を受診する目安
4.2 治療方法
5 まとめ
早く寝たいのになかなか眠れない…という経験はありませんか?
もしかすると、ストレスや睡眠習慣の問題などによって、寝つきが悪くなっているのかもしれません。
この記事では、寝つきが悪くなる原因についてだけでなく、寝つきをよくする対処法や、寝つけないときにどう過ごせばよいかもまとめています。
疲れているのになぜか寝つきが悪い、と感じている方はぜひ参考にしてみてください。
| 寝つきが悪い原因
眠りに就くまでの時間には個人差がありますが、大体30分~1時間以内に眠れていれば、あまり問題を感じることはないでしょう。
しかし、1時間以上寝つけないことが続いている場合、以下の原因が考えられます。
・睡眠を妨げるような行動や習慣がある
・寝つけないことに焦ってしまい悪循環に陥っている
これらの原因について、ひとつずつ解説します。
| ストレスを感じている
誰しも一度はストレスを感じる出来事がきっかけで眠れなくなったことがあるのではないでしょうか。
ストレスによって一時的に寝つきにくくなるのはよくあることで、それだけでは大きな問題にはなりません。
しかしストレスが慢性的に続いていたり、あまりに大きなストレスだったりする場合、寝つきにくい状態が続くこともあります。
| 睡眠を妨げる行動や習慣
日常生活の中で何気なく行っている行動が、実は睡眠を妨げていることがあります。
以下のような習慣に心当たりがないか、チェックしてみましょう。
– カフェインやアルコールの摂取
眠気覚ましにコーヒーを飲む方法があるように、コーヒーなどに含まれる成分であるカフェインには覚醒作用があります。
また、アルコールは寝つきをよくすると考えて寝酒(寝る直前までお酒を飲む)を習慣としている方もいらっしゃいますが、実はアルコールは一時的に眠くなっても、その後の眠りを浅くしてしまう作用があります。
– 入浴時間
入浴は正しく行えば睡眠によい影響を及ぼすといわれています。
しかし熱すぎるお湯に長時間浸かったり、寝る直前に入浴したりすると、上昇した体温がなかなか下がらず寝つきにくくなる可能性があります。
– 就寝前のゲームやスマートフォン

寝る直前までゲームやスマートフォンなどの明るい光を見続けると、眠気を感じさせるメラトニンという成分の分泌が少なくなることがわかっています(※)。
海外の実験では、寝る前にタブレット端末で電子書籍を読んだ人よりも、紙媒体の書籍を読んだ人たちは平均で10分寝つくのが早かったそうです。
さらに、強い光の影響だけでなく、ゲームやスマートフォンの利用によって脳が興奮状態になったり、仕事のメールを見てしまうことで不安や心配が出てくるなど、寝つきにくくなるきっかけが生まれやすくなるでしょう。
(※)A. Chang, D. Aeschbach, J.F. Duffy, & C.A. Czeisler, Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 112 (4) 1232-1237, https://doi.org/10.1073/pnas.1418490112 (2015).
– 日中の活動
自然と眠気を感じるためには、日中にほどよく体の疲労をためるのが重要です。
しかし、寝つきが悪かった翌日「昨日あまり眠れていないから少しでも休もう」と考えて日中に仮眠をとったり、動くのが億劫だからと外出や活動を避けてしまう方もいます。
そして、これらの行動がさらに寝つきを悪くさせてしまうのです。
| 寝つけないことへの焦り
寝つけないことが気になると、翌日の予定のことを考えて焦ってしまいがちです。
よくある例が、たびたび時計を見てしまい「もうこんな時間だ」「早く寝なければいけないのに」と焦り、不安や緊張感が高まることで余計に心身が興奮状態となり眠れない、という悪循環でしょう。
| 寝つきをよくするための対処法
寝つきが悪い原因に心当たりがある方は、以下の内容を参考に対処してみてください。
| ストレスへの対処
ストレスを感じて寝つきが悪くなっている場合、まずストレスそのものへの対処が必要です。
すぐに解決することが難しい問題であれば、誰かに気持ちを話して気持ちを落ち着かせたり、少し休みをとるなどしてストレスの原因から一度離れてみることも役立つかもしれません。
| 睡眠を妨げる習慣の改善
夜の睡眠を妨げる習慣に当てはまるという方は、習慣を変えてみるといいでしょう。
改善のポイントを解説します。
– 寝る前のカフェインやアルコールを避ける
カフェインを摂る場合は寝る3~4時間前までにしましょう。
また、アルコールの摂取も就寝前2~3時間前までとすることをおすすめします。
– 入浴時間

入浴と睡眠の関係についてはこれまでにさまざまな研究がされてきました。
海外の研究で、入浴が睡眠に与える影響について調べた13件の研究結果をまとめた報告があります(※)。
これによると、寝る1~2時間前に40~42.5℃の湯船に10分以上浸かることで、寝つくまでの時間が短くなり、睡眠の質もよくなることが示されました。
(※)Haghayegh S, Khoshnevis S, Smolensky MH, Diller KR, Castriotta RJ. Before-bedtime passive body heating by warm shower or bath to improve sleep: A systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev. 2019 Aug;46:124-135. doi: 10.1016/j.smrv.2019.04.008. Epub 2019 Apr 19. PMID: 31102877.
– 就寝前のゲームやスマートフォン
スマートフォンを目覚まし代わりに枕元に置いて寝る方もいると思いますが、睡眠の質だけでいえばあまりおすすめはできません。
枕元に置いてあると、
・着信音が鳴ったとき
・ふと疑問を感じて調べたいことが出てきたとき
・買い物リストなど、メモしておきたいことが思いついたとき
・予定を確認したくなったとき
などでつい手に取り、結果的に寝る直前までスマートフォンを見てしまいがちになります。
寝る1時間前には通知をオフにするなどして着信や通知が気にならないように工夫してみましょう。
– 日中の活動

あまり眠れていないと感じている場合でも、なるべく日中は活動するようにしましょう。
午前中の太陽光を浴びることは、自然とずれてしまう体内時計をリセットしてくれ、夜になると眠気を感じさせるメラトニンの分泌を促してくれます。
また、午前中に太陽光を浴びながら適度に運動することは寝つきをよくすることもわかっています(※)。
ただし、夜間に激しい運動を行うとかえって睡眠の質を低下させるといわれているので、注意しましょう。
(※)本邦の睡眠関連問題と その予防・改善に資する運動の可能性
| 眠らなければと考えすぎない
眠れないときには、「早く寝なければ」と自然と考えてしまうものです。
しかし、国内で行われた実験(※)では、眠くなったら眠るよう指示された群と、できるだけ早く眠るよう指示された群の脳波を測定した結果、できるだけ早く眠るよう指示された群のほうが寝つくまでに時間がかかりました。
早く眠ろうと努力することで、かえって寝つきを悪くしてしまうのです。
(※)入眠への努力が入眠過程に及ぼす影響
| 寝つけないときはどうしたらいいのか
それでは、布団に入っても30分~1時間以上寝つけないときは、どうすればいいのでしょうか。
| 寝床から出る
まずは、眠れないときにそのまま寝床に居続けることはやめましょう。
寝つけないことに苦痛を感じてきたら一度寝床から出て、本を読んだり温かい飲み物を飲んだりして、疲労につながらないような行動をとるのがよいです。
| 考え事への対策
考え事をしてネガティブな気分になってしまっているときは、気分が変わるような行動をとるとよいでしょう。
効果的な気分の変え方には個人差がありますが、好きな音楽を聴いたり、軽いストレッチや呼吸法などで心身の緊張をほぐすのも効果的です。
ストレッチや呼吸法を実践するときは、体が伸びている感覚や空気が体に入ったり出ていく感覚に注意を向けると、余計な考え事から距離を置くことができます。
| しないほうがいいこと
寝つけないからといって寝床から出てゲームをしたり動画を見たり、仕事をしたりすることは覚醒を促進してしまうので避けましょう。
また、食事をとることも消化器官の負担になり、睡眠の質も低下します。
どうしても空腹が気になる場合は温かい飲み物やスープなどがよいです。
| 寝つきの悪さは治療できる?
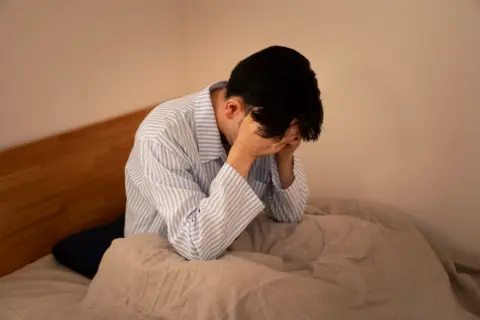
寝つきの悪い状態が続き日常生活に支障が出ている場合、不眠症の可能性があります。
不眠症は、医療機関での治療が可能です。
| 不眠症とは
不眠症は、何らかの睡眠問題があり、そのために日中の倦怠感や集中力低下などの不調が出てしまう病気です。
この状態が続くと日常生活にも支障が出てしまうこともあるため、医療機関の受診を検討しましょう。
不眠症は、困っている症状によって
・中途覚醒(夜中に目が覚め、その後再び眠れなかったり、何度も目が覚めてしまう)
・早朝覚醒(朝早くに目が覚めてしまう)
のタイプに分けられます。
一般成人のうち3~4割が何らかの睡眠問題に悩んでいるといわれ、実は不眠症はごく一般的な病気なのです。
| 医療機関を受診する目安
寝床に入っても30分~1時間以上寝つけない日が週に3日以上あり、それが3か月以上続くようであれば受診を検討しましょう。
3か月以上続いていなくても、寝つけないことで日中の活動や気分に影響が出ている場合にも受診を考えてもよいかもしれません。
当院でも、オンラインで不眠症の治療が可能です。睡眠のことで悩んでいる方はお気軽にご相談ください。
| 治療方法
不眠症の治療は、主に薬物療法と生活習慣の改善によって行われます。
薬を使う場合、睡眠導入剤とよばれる薬剤を用いるのが一般的です。
睡眠導入剤には、効果の持続時間によって種類が分けられており、寝つきの悪い症状が主であれば、効果時間の短いタイプの薬剤が選択されることが多いでしょう。
薬が合わない、あるいは薬を使うことに抵抗がある場合は、生活習慣や睡眠習慣の見直しなどを行うこともあります。
また、不眠症以外の疾患が原因の場合、原因である疾患の治療によって、寝つきの悪さが改善するかもしれません。
| まとめ
寝つきが悪くなる原因には、ストレスや睡眠を妨げる行動や習慣、寝つけないことへの焦りなどが挙げられます。
さらに、睡眠を妨げる行動や習慣には、
・入浴時間
・就寝前のゲームやスマートフォン
・日中の活動
などが関係しています。
当てはまる原因や習慣に合わせて、
・就寝前のアルコールやカフェインを避ける
・入浴は寝る1~2時間前まで、40~41℃の湯船に浸かる
・就寝前のゲームやスマートフォンを避ける
・日中はなるべく太陽光を浴びて適度に運動する
・眠らなければと思いすぎない
などの対処を行うとよいでしょう。
それでも寝つきの悪さが続く、日中の活動に支障が出ていると感じる場合は、無理せず早めに医療機関の受診を検討してみてください。
当院でもオンラインにて不眠症の治療が可能ですので、皆様の快適な睡眠や生活のお役に立てれば幸いです。
参考文献
- 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 不眠症(睡眠障害)|こころの情報サイト
- 厚生労働省 休養・こころの健康 e-ヘルスネット
- PNAS A. Chang, D. Aeschbach, J.F. Duffy, & C.A. Czeisler, Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 112 (4) 1232-1237, https://doi.org/10.1073/pnas.1418490112 (2015).
- PubMed Haghayegh S, Khoshnevis S, Smolensky MH, Diller KR, Castriotta RJ. Before-bedtime passive body heating by warm shower or bath to improve sleep: A systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev. 2019 Aug;46:124-135. doi: 10.1016/j.smrv.2019.04.008. Epub 2019 Apr 19. PMID: 31102877.
- 森田(2023). サイエンスへの招待「本邦の睡眠関連問題とその予防・改善に資する運動の可能性」理大 科学フォーラム 435.36-41.
- 林 他(2021). 入眠への努力が入眠過程に及ぼす影響 生理心理学と精神生理学 39(1),52‒64.