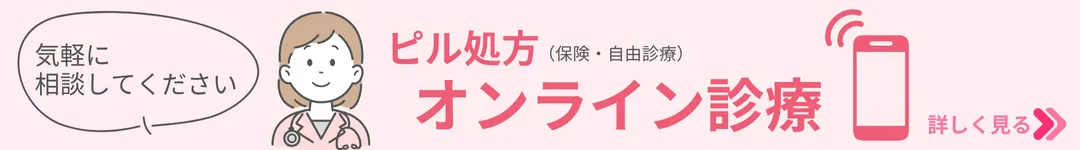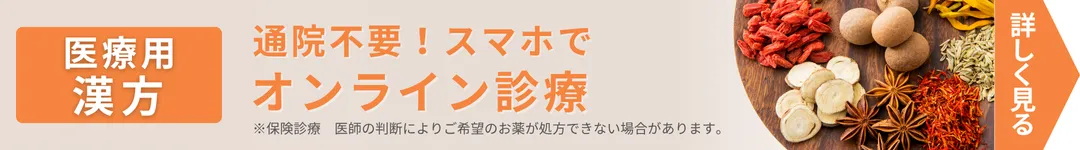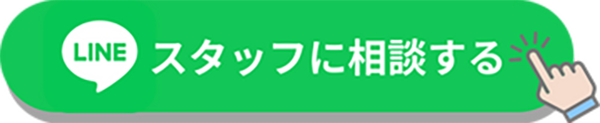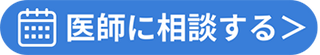低用量ピルの副作用が怖い方へ~症状と対処を正しく知ろう~
ホーム > ブログ


日本赤十字社医療センター、虎の門病院で産婦人科医として臨床経験を積む。「忙しい女性がもっと気楽に相談できる場所を作りたい」との想いを胸に、2024年11月、オンライン診療専門のシンクヘルスクリニックを開院。
婦人科(生理痛・更年期)、皮膚科、医療用漢方など、女性ならではの悩みに幅広く対応。心のケアも大切に、一人ひとりが安心して自分の体と向き合えるようサポートしている。
目次
1 低用量ピルとは
1.1 効果
1.2 ピルの種類と違い
2 主な副作用と対処
2.1 吐き気・嘔吐・悪心
2.2 不正出血
2.3 むくみ・体重増加
2.4 腹痛・頭痛
2.5 乳房の張り
2.6 血栓症
2.7 がんのリスク
3 副作用はいつまで続くの?
4 副作用が出やすい人の特徴
4.1 吐き気・頭痛・むくみなどが出やすい人
4.2 血栓症のリスクが高い人
4.3 ピルが合うかどうかは「相性」も大切
5 まとめ
今までピルを使ったことがない方が副作用が怖いと思うのは無理もないことです。しかし、ピルだけでなく、どんな薬にもよい作用と副作用の2つの面があるのです。
低用量ピルは、ピルの中でも比較的副作用が出にくいタイプですが、体質によって副作用を感じやすい人もいます。
今回は副作用としてどんな症状が出る可能性があるのか、またどう対処すればよいかを解説します。どうぞ最後までお付き合いください。
| 低用量ピルとは

低用量ピルは黄体ホルモンと卵胞ホルモンという2つの女性ホルモンが配合されている薬です。
副作用を起こりにくくするために、ホルモン量をできるだけ少なくしているものを低用量ピルといいます。
| 効果
低用量ピルの主な効果として
・避妊
・生理痛や月経前症候群(PMS)などの緩和
・生理周期を整える
・ニキビや肌荒れの改善LDL(悪玉)
などがあります。
低用量ピルを服用すると、体内で分泌されるホルモンの量が減るため、
・排卵が抑制される
・子宮内膜が厚くならない
といった変化がおきます。この変化が上記の効果につながるのですが、同時にマイナートラブルという副作用が出ることもあります。
| ピルの種類と違い
ピルというと、一般的に低用量ピルを示すことが多いですが、実はいくつか種類があります。
女性ホルモンの配合量の違いによって、それぞれの目的や副作用の出やすさに違いがあります。
| ピルの種類 | 女性ホルモンの配合量 | 主な目的 | 副作用の出やすさ |
| 中用量ピル | やや多い | 生理周期の調整 | 比較的出やすい(吐き気30~50%) |
| 低用量ピル | 中くらい | 避妊
生理痛を和らげる |
比較的少なめ(吐き気10~30%) |
| 超低用量ピル | とても少ない | 生理痛を和らげる | 少なめ(吐き気10~20%) |
表の通り、含まれているホルモン量が少ないほど、副作用は出にくいとされています。しかし、ホルモン量が少ないピルを服用していても、体質によって副作用が出てしまう場合はあり、一概にはいえません。
ピルを飲むことでどんな悩みを解決したいかや、副作用の程度などを医師と相談しながら適切な薬を選択していきます。
なお、副作用の多くは、服用を始めて1〜3か月ほどで落ち着くとされていますが、もし辛い症状が長く続く場合や生活に支障が出る場合には、医師に相談して別の種類のピルに変更することも検討できます。
関連記事
生理はストレスで遅れる?早まる?~生理周期を整える方法を解説~
生理を遅らせる方法とは?ピルを飲み始めるタイミングや副作用について解説
| 主な副作用と対処

ピルにはたくさんのメリットがある一方、副作用(マイナートラブル)が気になるという方もいます。よくある症状と対処についてまとめました。
| 吐き気・嘔吐・悪心
ピルを飲み始めた頃に最も起こりやすいマイナートラブルが、吐き気や嘔吐、悪心などです。ピルを飲み始めてホルモンバランスが変化することにより、胃腸の働きが悪くなるのが影響していると考えられます。個人差はありますが、2〜3か月間、ピルを服用することで症状が落ち着く方がほとんどです。
どうしても吐き気がひどいときには、以下のような対処を取ってみましょう。
・吐き気止めを飲む
ピルと吐き気止めは基本的に併用可能です。ピルを処方してもらうときに医師に相談してみましょう。
・服用時間を変えてみる
ピルは適切な効果を得るために、毎日同じ時間に服用するのが望ましいです。ご自身の生活リズムに取り入れやすい時間帯であれば何時でも服用可能です。
副作用が気になる方は、夕食後や就寝前に服用すると、寝ている間に副作用のピークが過ぎるので、症状が出にくいといわれています。
ご自身に合ったベストな服薬のタイミングを探してみましょう。
| 不正出血
ピルを服用中の方の20~30%が不正出血を経験するといわれています。不正出血はピルを飲み始めたばかりの頃や、飲む時間が遅れたり、飲み忘れたりしたときに起こりやすいとされています。
ピルを飲み忘れると、一時的に体内の女性ホルモン量が減り、体がそろそろ生理を起こさなければと勘違いしてしまうのです。
不正出血の対策としては、
・決まった時間に忘れずにピルを服用し続ける
飲み始めの不正出血は、2~3か月程度服用を続けることで、治まる方がほとんどです。アラームを設定するなど、飲むタイミングを忘れないようにする工夫を取り入れてみましょう。
・出血量が多かったり、なかなか不正出血が止まらない場合は医師に相談する
ピルの影響による不正出血は、少量であることが多いです。出血量が多い場合には、子宮や卵巣などの疾病の可能性も考えられますので、一度医療機関に相談してみましょう。
などを取り入れてみましょう。
| むくみ・体重増加
ピルを飲むと太るという噂を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、ピル自体に太る成分は含まれていません。
しかし、副作用であるむくみによって、太ったように感じたり、実際に体重が増えてしまうことはあります。
また、ピルに含まれている黄体ホルモンは食欲が増す作用があるため、つい食べ過ぎてしまって体重が増えてしまうこともあるでしょう。
むくみや体重増加が気になるときは
・適度な運動で血のめぐりをよくする
・ぬるめのお湯に浸かり、体を温める
・塩分を控える
などの工夫を取り入れてみましょう。
関連記事
ピルを飲むと太るって本当?2つの理由と対策・よくある質問を解説
食べていないのに太る原因は?~急な血糖上昇や隠れたカロリー摂取~
| 腹痛・頭痛
副作用として腹痛(下腹部痛を含む)や頭痛が起きる可能性もあります。吐き気などの症状と同じく、女性ホルモンのバランスが変わることによる一時的な体の反応です。
対処方法
・症状の変化を観察する
激しい腹痛・頭痛の場合は後述する血栓症の初期症状である場合や、婦人科関連ではない別の疾患である可能性もあります。まずは安静にして、症状をよく観察し、いつもと違う痛みであれば受診を検討しましょう。
・鎮痛剤を服用する
辛い場合は痛み止めを処方してもらうのもよいでしょう。薬の飲み合わせによっては、ピルの効果を強め、副作用が出やすくなるものもあります。市販薬を飲む場合も、薬剤師にピルを服用していることを伝え、相談してみるのが安心です。
| 乳房の張り
ピルによって血中の女性ホルモン値が上昇し、胸の張りが起こることがあり、人によっては痛みを感じる方もいます。
対策としては、
・締め付けが少ない下着を着用する
・入浴などで体を温める対処方法
など痛みを和らげる工夫を取り入れてみてください。
ピルの服用を続けることにより、症状が落ち着いてくることがほとんどですが、痛みだけでなく、しこりが気になる場合は乳がんなど、他の病気の可能性もあるため、早めに医療機関を受診しましょう。
| 血栓症
副作用の中でも最も注意すべきなのは血栓症ですが、ピルを服用中であっても、1年で1万人に3~9人という発生頻度で、それほど高くありません。
なお、妊娠中は血栓症のリスクが1万人あたり5〜20人程度といわれており、実はピルによるリスクより高いというデータもあります。血栓症のリスクが特にない健康な人がピルを服用する場合には、過度に不安になる必要はありません。
ただし、以下のような血栓症のリスク因子がある方は、ピルの服用に注意が必要です。
・喫煙している(特に35歳以上の方)
・肥満がある(BMI30以上)
・前兆を伴う片頭痛がある
・家族に血栓症の既往がある
これらに当てはまる方は、服用の可否を慎重に判断する必要がありますので、必ず医師に相談してください。問診や必要に応じた検査を行ったうえで、医師が安全性を確認して処方を行います。
もしピルを服用中に以下の症状が出た場合には、血栓症の初期症状である可能性がありますので、すぐに医療機関の受診が必要です。ピルを処方された医療機関以外にかかるときは、ピルを服用中であることを伝えましょう。
・激しい腹痛、頭痛
・強い胸の痛み、呼吸困難
・目が見えにくくなる
・ふくらはぎの怠さ、むくみ
血栓症の発症予防には、こまめに水分補給をしたり、着圧ソックスを履くなどして足の血液が心臓に戻るのをサポートするのもよいでしょう。
| がんのリスク
ピルを飲むことによって、がんのリスクは上昇するものと、低下するものの両方があります。
乳がんはピルを内服していない人と比べて発症リスクが1.2倍になるという報告がありますが、ピルをやめてから5~10年でリスクは元に戻るといわれています。
また、子宮頸がんは、ピルの使用期間が5年以上になると、発症リスクが1.5倍になるという報告がありますが、乳がんリスクと同様にピルを中止後10年以内にリスクは元に戻るといわれています。
ピルの服用中は、1年に1回はがん検診を受けておくと安心です。
一方で、卵巣癌と子宮体がんの発症リスクは半分程度に低下し、この予防効果はピルを中止した後も10年以上続くという報告があります。
関連記事
ピルは乳がんのリスクになる?その他のがんとの関係も医学的に解説
| 副作用はいつまで続くの?

上記の副作用のほとんどは、ピルを飲み続けることで、症状が改善する方が多いといわれています。飲み始めて1~3か月程度で治まってくる場合が多いようです。
副作用が気になり、生活に支障を来している場合や、血栓症を疑うような症状が出ている場合には、医師に相談しましょう。
また、副作用が辛い場合には、違う種類の低用量ピルに変更したり、さらに女性ホルモンの配合量が少ない超低用量ピルを試すなどの選択肢もあります。
体質と薬の成分の相性によって、合う・合わない薬がありますので、1種類だけ試して「自分にはピルは合わない」と判断してしまうのではなく、医師とよく相談するのがよいでしょう。
| 副作用が出やすい人の特徴
副作用の種類によって、症状の出やすい人の特徴は異なります。
副作用の内容によってリスクが異なるため、気になる症状がある方は、あらかじめ医師に相談しておくと安心です。
| 吐き気・頭痛・むくみなどが出やすい人の特徴
これらはピルを服用し始めたときにホルモンバランスの変化に体が慣れていないことが主な原因とされています。以下のような方は、このような副作用を感じやすい傾向があります。
・もともと月経前に吐き気・頭痛・むくみが起こりやすい方
・片頭痛がある方(特に前兆のない片頭痛)
・自律神経が不安定になりやすい方(ストレスがたまりやすいなど)
これらの症状は多くの場合、1〜3か月程度で自然に落ち着くことが多いですが、つらい場合は医師と相談のうえ、別のタイプのピルへ変更することも可能です。
| 血栓症のリスクが高い人
血栓症はまれですが、重篤な副作用であり、服用前の問診でリスクが高いと判断された場合は処方されないこともあります。以下の項目に当てはまる方は、慎重な評価が必要です。
・40歳以上
・喫煙習慣がある(特に35歳以上での喫煙)
・肥満(BMI30以上)
・高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病がある
・家族に血栓症になったことがある方がいる
・前兆のある片頭痛(視野のちらつきなどを伴う場合)
このような方は、ピルの服用自体が推奨されないこともあります。服用の可否は、医師が全身状態や生活習慣も含めて総合的に判断します。
| ピルが合うかどうかは「相性」も大切
同じ種類のピルでも、「合う」「合わない」は人それぞれです。副作用がつらいときに「ピルは自分に合わない」と諦めず、別の成分を含むピルに切り替えることで快適に使えるケースも多くあります。
また、ピルを服用できない方や副作用が強くて飲み続けられない方も、生理に伴うトラブルを漢方薬で緩和するという方法もあります。月経前症候群(PMS)の症状を和らげるのに役立つ漢方薬もありますので、検討してみてもよいでしょう。
関連記事
PMS(月経前症候群)の症状を和らげる漢方薬とは~特徴から飲み方まで解説~
| まとめ
低用量ピルは、避妊だけでなく生理痛やPMSの緩和など、女性の毎日をサポートしてくれる選択肢のひとつです。一方で、体質によっては副作用が出ることもあり、不安を感じる方もいるかもしれません。
多くの副作用は一時的なもので、ちょっとした工夫で軽減できることもあります。
大切なのは、自分の体と向き合いながら、無理なく続けられる方法を見つけることです。
不安なときは「こんなことで受診してもいいのかな?」と迷うこともあるかもしれませんが、小さなことでも医師に相談することで、安心につながります。気になる症状があるときは、ひとりで抱え込まず、遠慮せずに相談してみてくださいね。
本記事が、低用量ピルの服用を考えている方にとって、安心してピルを服用するのにつながりますと幸いです。