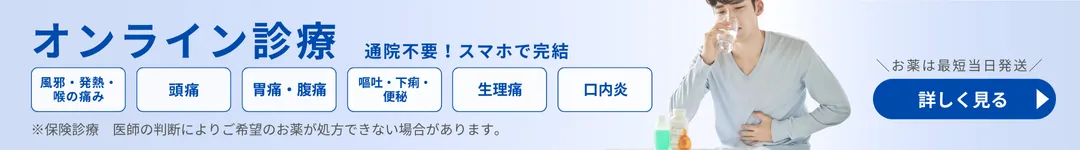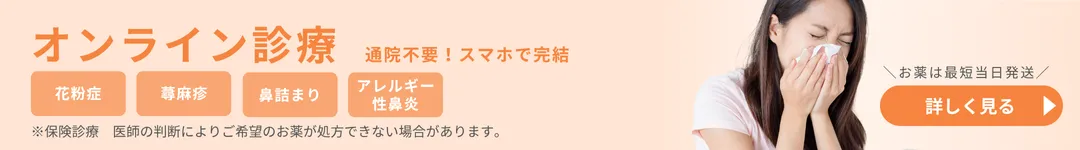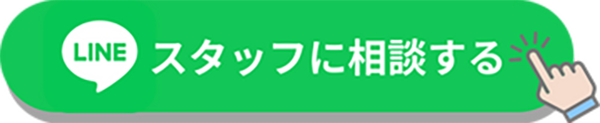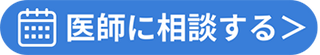風邪と花粉症の見分け方は?受診すべき診療科や治療・予防方法について解説
ホーム > ブログ


日本赤十字社医療センター、虎の門病院で産婦人科医として臨床経験を積む。「忙しく頑張っている人がもっと気楽に相談できる場所を作りたい」との想いを胸に、2024年11月、オンライン診療専門のシンクヘルスクリニックを開院。
内科、皮膚科、医療用漢方、婦人科など、受診者の悩みに幅広く対応。心のケアも大切に、一人ひとりが安心して自分の体と向き合えるようサポートしている。
目次
1 風邪と花粉症の症状の違い・見分け方
1.1 鼻の症状
1.2 目の症状
1.3 頭痛の症状
1.4 その他の症状
1.5 発症時期や症状の出方
2 風邪または花粉症の疑いがある場合は何科を受診すべき?
2.1 基本的には内科を受診すればよい
2.2 耳鼻科を受診すべきケース
2.3 眼科を受診すべきケース
2.4 アレルギー科を受診するべきケース
3 風邪の対処方法・予防方法
3.1 風邪症状を和らげる方法
3.1.1 薬物療法
3.1.2 免疫力を高める
3.2 風邪の予防方法
4 花粉症の検査・対症療法・予防方法
4.1 花粉症の検査方法
4.2 花粉症の対症療法
4.2.1 薬物療法
4.2.2 アレルゲン免疫療法
4.2.3 手術
4.3 花粉症の予防方法
5 まとめ
風邪と花粉症は症状が似ているため、特に花粉が飛散する時期はどちらの症状なのか迷ってしまう方も少なくありません。
どちらも似た症状を持ちますが、くしゃみや鼻水の状態、発症の経緯など細かな違いを理解すれば、見分けることが可能です。
この記事では、風邪と花粉症の見分け方について解説します。
風邪と花粉症の検査・治療・予防方法や受診すべき診療科などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
| 風邪と花粉症の症状の違い・見分け方

風邪と花粉症の主な症状として鼻・目・頭痛の症状が挙げられます。
ここではそれぞれの症状の違い・見分け方について解説します。
| 鼻の症状
風邪と花粉症はどちらも鼻の症状が現れますが、それぞれ以下のような特徴があります。
| 風邪 | 花粉症 | |
| 鼻の症状 | くしゃみ、鼻水、鼻づまり | アレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎によるくしゃみ、鼻水、鼻づまり |
| 鼻水の色や粘度 | 初めは透明でさらさらしているが、数日経過すると黄色や緑色の粘性のあるものに変わることが多い | 透明でさらさらとしており、色が変わることはない |
特に見分けやすいポイントは、鼻水の色や粘度です。
風邪は数日経過すると黄色や緑色の粘性のあるものに変わることがありますが、花粉症はそのような色の変化は基本的にみられません。
また花粉症は、風邪には見られない『即時反応』や『遅発相反応』があります。
即時反応:アレルギーの原因物質が体内に入り込んでから数分~数十分の短時間で起こる症状
遅発相反応:花粉がない状態でも症状が現れること。アレルギー細胞から放出される物質によって神経や血管が刺激され、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が起こる
さらに花粉症ではくしゃみが連続して起こることが多く、1日に10回以上のくしゃみが続くこともあります。
| 目の症状
風邪の場合は目の症状がほとんど現れないため、目のかゆみや充血といった症状が現れたら、花粉症の可能性が高いと考えてよいでしょう。
花粉症では目のかゆみ、充血、涙目などの症状が現れます。
これらの症状は花粉が目の結膜に付着し、アレルギー反応を引き起こすために起こるものです。
目に強いかゆみを感じて擦ることが多いですが、擦ることで症状が悪化することがあるため、注意が必要です。
また目の症状は、花粉の飛散が多い時期に悪化しやすい傾向があります。
| 頭痛の症状
風邪では、発熱や全身の倦怠感に伴い、頭痛が生じることがあります。
一方、花粉症でも頭痛が生じることがありますが、これは主に鼻づまりによるもので、鼻づまりが続くと副鼻腔の換気が悪くなり、圧迫感や頭痛を引き起こすことがあります。
しかし花粉症による頭痛は、風邪によるものよりも軽度であることが一般的です。
| その他の症状
風邪の一般的な症状には喉の痛み、咳、発熱、全身の倦怠感などがあります。
特に発熱は風邪の特徴的な症状の一つで、体温が37.5℃以上まで上昇することがあります。
一方、花粉症では喉のかゆみや違和感、咳が生じることがありますが、発熱は通常見られません。
また花粉症の症状として、喉のかゆみ、咳、鼻づまりによる睡眠障害、倦怠感などが挙げられます。
そのほかにも気分が晴れない、いらいら感、憂うつ、思考力・記憶力の低下など、日常生活に支障が出るような症状が現れることも少なくありません。
関連記事
喉がかゆいのは花粉症が原因?~症状や対処法・薬について解説~
| 発症時期や症状の出方
風邪は季節を問わず一年中発症する可能性があり、特に気温の変化が激しい季節の変わり目に多く見られます。
症状はウイルスに感染してから1~3日以内に現れ、通常1週間程度で自然に回復します。
一方、花粉症は特定の季節にのみ症状が現れるのが特徴です。
花粉症の約70%はスギ花粉症といわれています。
スギ花粉が飛散する時期は地域によって異なりますが、関東エリアは1月上旬から4月いっぱいにかけてです。
症状は花粉の飛散が始まるとすぐに現れ、飛散が終わるまで続くことが一般的です。
また花粉症の症状は、花粉の飛散量や個人の体質によって強さが変わります。
さらに花粉の飛散量が多い年には重症化しやすく、少ない年には軽減する傾向があります。
| 風邪または花粉症の疑いがある場合は何科を受診すべき?

風邪または花粉症の疑いがある場合は、基本的に内科を受診するとよいでしょう。
ただし耳鼻科や眼科を受診すべきケースもあり、症状に合った診療科を受診することが大切です。
ここでは、風邪または花粉症の疑いがある場合に受診すべき診療科について解説します。
| 基本的には内科を受診すればよい
風邪か花粉症か判断がつかない場合や、発熱・全身倦怠感を伴う場合は、まず内科を受診するのが一般的です。
内科では問診や診察を通じて、ウイルス感染による風邪か、アレルギー反応による花粉症かを判断します。
風邪の場合は、解熱鎮痛剤や咳止め、抗生剤(細菌感染が疑われる場合)などが処方されます。
一方、花粉症の可能性がある場合は、抗アレルギー薬を処方し、必要に応じて専門科の受診を勧められることもあります。
| 耳鼻科を受診すべきケース
鼻づまりやくしゃみ、鼻水などの症状が特に強い場合や、慢性的な副鼻腔炎の疑いがある場合は、耳鼻科の受診が適しています。
耳鼻科では鼻の粘膜の状態を詳細に確認し、必要に応じてアレルギー検査を行うこともあります。
花粉症が重症化し鼻づまりがひどい場合は、点鼻薬やレーザー治療など、より専門的な治療を受けられるのも耳鼻科の強みです。
また風邪による鼻づまりが長引き、副鼻腔炎を併発している場合も、耳鼻科で適切な治療を受けられます。
| 眼科を受診すべきケース
目のかゆみ、充血、涙目といった症状が特に強い場合は、眼科を受診すると適切な治療を受けられます。
眼科では抗アレルギー点眼薬や抗炎症点眼薬を処方してもらえるため、花粉症により引き起こされる結膜炎にも有効です。
市販の目薬では十分な効果が得られない場合や、目のかゆみがひどく日常生活に支障をきたす場合は、眼科での治療を検討するとよいでしょう。
また風邪によるウイルス性結膜炎が疑われる場合も、眼科での受診を検討してみましょう。
| アレルギー科を受診するべきケース
花粉症の症状が毎年ひどく、抗アレルギー薬では十分に効果が得られない場合や、他のアレルギー症状を併発している場合は、アレルギー科の受診が適しています。
アレルギー科では、血液検査や皮膚テストを用いたアレルギー検査を実施し、原因となるアレルゲンを特定することができます。
さらに症状に応じて舌下免疫療法などの長期的な治療方法を提案してもらえるため、重度の花粉症患者さんにとって有効な選択肢となるでしょう。
| 風邪の対処方法・予防方法

ここでは風邪の対処方法・予防方法についてそれぞれ解説します。
| 風邪症状を和らげる方法
風邪の症状を和らげる方法は『薬物療法』と『免疫力を高める』の2つです。
– 薬物療法
薬物療法は、風邪の症状を緩和するための対処方法です。
解熱鎮痛剤や咳止め、鼻づまりを改善する薬などが処方されます。
また抗菌薬が処方されるケースもあります。
– 免疫力を高める
風邪の予防には、免疫力を高めることが重要です。
十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動など、健康的な生活習慣を維持することで、免疫系の機能をサポートできます。
またストレスの管理も免疫力維持に重要な要素です。
適度に体を動かしたり趣味を見つけて楽しんだりするなどして、ストレスをため込まないようにしましょう。
| 風邪の予防方法
風邪を予防するためには、手洗い・うがいや健康的な生活習慣を意識することが大切です。
手洗いは、風邪の予防において最も基本的で効果的な方法の一つです。
外出先から帰宅した後や食事前など、こまめに石鹸と水で手を洗うことで、ウイルスの拡散を抑えるのに役立ちます。
またうがいも手洗いと同じくらい重要です。
日本で行われた研究では、水によるうがいが風邪の発症率を約40%低下させることが示されています。
この研究は387名のボランティアを対象に、水うがい群、ヨード液うがい群、うがいをしない群の3群に分けて行われ、水うがい群で有意な予防効果が確認されました。
最終的にこの研究での100人中の風邪の発症率は、水うがい群で17人、ヨード液うがい群で23.6人、うがいしない群で26.4人となったのです。
群間のばらつきを揃えると、水うがいをした場合の発症率は、うがいをしない場合に比べて40%も低下することになります。
また適切な栄養摂取、十分な休息、適度な運動など、全体的な健康状態を維持することも、免疫力を高め、風邪の予防に大切なポイントです。
さらに混雑した場所を避ける、マスクの着用、室内の適切な湿度を保つなどの対策も、風邪対策の一つになります。
これらの治療法と予防策を組み合わせることで、風邪の発症リスクを低減し、重症化を防ぐ効果が期待できます。
関連記事
風邪の予防方法や原因を解説~食べ物や飲み物での対策も~
| 花粉症の検査・対症療法・予防方法

花粉症の検査・対症療法・予防方法についてそれぞれ解説します。
| 花粉症の検査方法
花粉症の検査方法には、問診、鼻鏡検査、鼻汁好酸球検査、皮膚テスト、血清特異的IgE抗体検査、鼻粘膜誘発テストなどがあります。
・皮膚テスト:アレルギーを起こす物質を皮膚に少量付着させ、反応を確認する検査
・血清特異的IgE抗体検査:血清特異的IgE(アレルギー物質に対応して血液内に出来上がる抗体)の有無を調べる検査
・鼻粘膜誘発テスト:アレルギー性病変を起こした粘膜の反応を見る検査
上記の検査のうち、2項目が陽性であれば花粉症と診断されます。
| 花粉症の対症療法
花粉症の対症療法は『薬物療法』『アレルゲン免疫療法』『手術』などがあります。
– 薬物療法
薬物療法は、花粉症の症状を抑えるための対症療法です。
薬の種類や組み合わせを変えることで、患者さんに合った対症療法が可能になります。
・抗ロイコトリエン受容体拮抗薬:鼻詰まりが強いときや花粉により引き起こされる咳などに有効な薬
・抗アレルギー点眼薬:目のかゆみや充血に有効な薬
・ステロイド点眼薬:症状が特に強い場合に使用される薬
・鼻噴霧用ステロイド薬:花粉飛散前から使用することで症状を抑えられ、くしゃみ・鼻水・鼻づまりに有効な薬
薬にはそれぞれ注意点があるため、必ず医師の指示に従って使用しましょう。
関連記事
オンライン診療でできる花粉症対策とは?アレルギー治療薬についても解説
– アレルゲン免疫療法
アレルゲン免疫療法は、アレルゲンを含む治療薬をあえて体内に投与することで、アレルゲンに触れた際に引き起こされる症状を緩和する治療方法です。
薬物療法で改善しなかった患者さんにも効果が出る可能性があるほか、治療後もしばらく効果が持続するメリットがあります。
『舌下免疫療法』と『皮下免疫療法』の2種類があり、それぞれの特徴は以下の通りです。
・皮下免疫療法:注射でアレルゲンを投与する方法で、開始後半年間は数日~2週間毎の受診が必要
アレルゲン免疫療法は症状の改善率が高く、約8割の患者さんで改善が見られます。
– 手術
花粉症の症状が重度の場合、凝固手術(鼻粘膜焼灼治療)が行われる場合があります。
微量の高周波電流によって鼻粘膜を焼灼することで、鼻水やくしゃみ、鼻づまりなどの症状を改善する治療方法です。
また手術後も、経口アレルギー治療薬や経口ステロイド薬などにより症状を抑える場合があります。
| 花粉症の予防方法
花粉症を予防するためには、眼鏡やマスクを着用することが大切です。
花粉症用の眼鏡はもちろん、通常の眼鏡でも十分予防効果が期待できます。
眼鏡をしているのとしていないのとでは、目に入る花粉量が大きく異なるため、花粉が増える時期はコンタクトレンズではなく眼鏡を着用するようにしましょう。
また視力に問題がない方の場合は、度数の入っていないダテメガネを着用することをおすすめします。
そのほか、花粉症の予防には以下の方法も有効です。
・花粉の飛散量が多いときは窓や戸を閉める
・外出時にはマスクや眼鏡を着用する
・帰宅時には衣服や髪をよく払ってから入室する
・洗顔・うがい・手洗いをする
・花粉が付きやすい毛織物の衣服やコートの着用を控える
上記を参考に、ぜひ日頃から花粉症予防を意識して生活してみてください。
| まとめ
風邪と花粉症は鼻水やくしゃみといった症状が似ていますが、粘度や色、症状の発生経緯などに違いがあり、見分けやすくなります。
症状を抑えるためには適切な治療を受ける必要があるため、風邪または花粉症の症状でお悩みの場合は早めに医療機関を受診しましょう。
当院では、オンライン診療を行っています。
お薬は最短当日薬局で受け取る(※)ことが可能であるため、風邪や花粉症の症状でお悩みの方はぜひご相談ください。
※院外処方:処方箋FAX送付後、薬局で受取(受取日時は薬局の状況によります) 院内処方:発送のみ
参考文献
- 日本内科学会雑誌 第97巻 第1号 かぜ症候群とその周辺疾患
- 京府医大誌 122(8),541~547,2013「かぜ」とはどういう病気なのか
- 厚生労働省 的確な花粉症の 治療のために(第2版)
- 耳鼻免疫アレルギー(JJIAO) 38(4): 120, 2020 抗ヒスタミン薬と風邪治療・アレルギー性鼻炎治療
- 東京大学 PRESS RELEASE 風邪への抗菌薬処方と関連する診療所の特性
- 水うがいで風邪発症が4割減少
- アレルギー性鼻炎における鼻汁中非特異的IgE 検査の診断学的有用性の検討
- 政府広報オンライン 政府の花粉症対策
- 鼻粘膜誘発テストの実際と問題点
- 日本アレルギー学会 アレルゲン免疫療法の手引き
- 日山 亨,吉原 正治 広島大学保健管理センター研究論文集 Vol. 34, 2018, 67-74 かぜ症候群の予防に関するメタ解析論文のレビュー