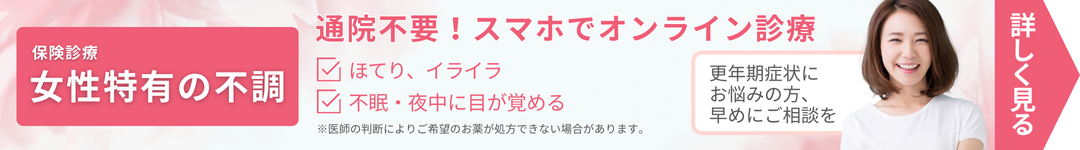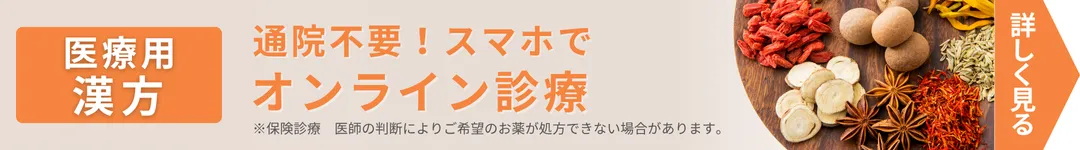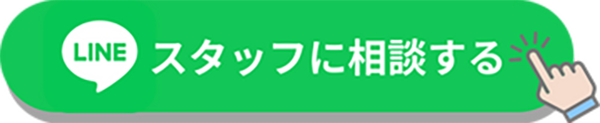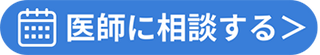冷えを緩和する漢方薬とは?~原因や温めるとよい部位を紹介~
ホーム > ブログ


日本赤十字社医療センター、虎の門病院で産婦人科医として臨床経験を積む。「忙しく頑張っている人がもっと気楽に相談できる場所を作りたい」との想いを胸に、2024年11月、オンライン診療専門のシンクヘルスクリニックを開院。
内科、皮膚科、医療用漢方、婦人科など、受診者の悩みに幅広く対応。心のケアも大切に、一人ひとりが安心して自分の体と向き合えるようサポートしている。
目次
1 足の冷えが起こる原因
1.1自律神経の乱れ
1.2痩せや筋肉量の低下
2 冷えに効果的な漢方薬を紹介
2.1 当帰芍薬散
2.2 加味逍遙散
2.3 桂枝茯苓丸
2.4 漢方薬の飲み方
2.5 医療用漢方薬という選択肢も
3 漢方以外の冷え対策法
3.1 ぬるめのお風呂で自律神経を整える
3.2 体を温める食材を取り入れる
3.3 運動によって筋肉量を増やす
3.4 ツボもオススメ
4 どこを温めるとよいのか
4.1 靴下の重ね履きは要注意
4.2 足だけ冷えるのは病気のサイン?
5 まとめ
「手足が冷えて眠れない」
「手足は冷たいのに顔は暑い」
体の冷えは、時に眠りを妨げてしまうほど私たちの生活に影響を与えます。どうにかしたい冷えには、漢方薬という選択肢があります。
では、どのような漢方薬が冷えに効果的なのでしょうか。
今回は、つらい冷えが起こるメカニズムから、冷えを和らげる漢方薬について解説します。
漢方薬以外にも役立つ冷え対策法もご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
| 冷えが起こる原因

冷えのタイプは4つがあります。
| 下半身型 | 足や下半身が冷える。上半身はのぼせる場合もある。 |
| 四肢末梢型 | 手足が氷のように冷たくなる。 |
| 内蔵型 | 体の表面は温かいが、体内は冷えている。 |
| 全身型 | 体の表面も内部も冷えている。 |
今回は、よくみられる原因についてご紹介します。
| 自律神経の乱れ
じつは、冷えの原因には自律神経(※)の乱れが関わっているのです。
(※)自律神経とは呼吸や血液の調節に関わる神経で、私たちが意識しなくても機能しています。
自律神経には交感神経と副交感神経があり、気分が興奮状態にあると交感神経が、リラックスした状態にあると副交感神経が優位になります。
しかし、ストレスや生活習慣の乱れなどさまざまな要因によって自律神経に影響があると、交感神経と副交感神経のバランスが崩れてしまうのです。
先ほどご紹介した冷えの4タイプは、それぞれ自律神経の乱れ方が異なります。
下半身型 :下肢末梢の交感神経優位
四肢末梢型:末梢の交感神経過緊張、中枢の交感神経優位
内蔵型 :末梢の交感神経弛緩、中枢の副交感神経優位
全身型 :中枢の交感神経優位
さらに、下半身型でも顔など上半身にのぼせのある場合は中枢の副交感神経が優位になっている可能性があります。
また、更年期には手足が冷えているものの顔はのぼせるといった症状があらわれますが、これらは更年期に起こるホルモンバランスの変化により、自律神経が乱れるために起こるものです。
| 痩せや筋肉量の低下
若い女性を中心にやせ型志向が強くある一方で、BMI(※)が20未満のやせ型も冷えの原因になるとわかっています。
※BMI(Body Mas Index)とは、身長と体重から算出される肥満度を表す指数のこと
さらに体温維持に欠かせない筋肉も、運動不足や加齢によって低下すると冷えにつながるのです。
ちなみに、男性よりも女性の方が冷えを感じるのは、筋肉量に男女差があるからだといわれています。
| 冷えに効果的な漢方を紹介
冷えが辛くて日常生活にも支障をきたす方は、漢方薬も選択肢の一つです。
体の冷えを和らげる効果が期待できる、代表的な漢方薬と冷えのタイプをご紹介します。
| 当帰芍薬散
むくみやすく、内蔵型のように腹部の冷えが気になる方に適しています。栄養を補って、元気にするイメージの漢方薬です。
| 加味逍遙散
ストレスや環境の影響で循環が悪くなっている方の自律神経を整える作用があります。
下半身型や四肢末梢型のように、全身ではなく四肢(とくに足)の冷えを緩和するのに有効という報告もあります。
| 桂枝茯苓丸
下半身は冷えているのに上半身はのぼせるという、いわゆる「冷えのぼせ」の症状がある方に適した漢方薬です。
血の巡りを整える作用があります。
| 漢方薬の飲み方
漢方薬は食前もしくは食間に服用するとよいでしょう。
なぜなら、漢方薬の中には食事内容によって効果に影響が及ぶものもあるからです。
| 医療用漢方薬という選択肢も
今回ご紹介した漢方薬は、いずれも市販でも手に入ります。しかし、漢方薬を選ぶ際に大事なことは、自分の症状にあっていて、かつ必要量を服用できるかどうかです。
医師に相談して処方される医療用漢方の場合は、あなたの症状に合わせた漢方薬を必要な分だけ処方できます。
選び方に迷った方は、一度医師に相談してみてはいかがでしょうか。
| 漢方以外の冷え対策法
漢方薬を飲むこと以外にも、冷えを和らげる方法はあります。
| ぬるめのお風呂で自律神経を整える
入浴は体の緊張をほぐしてリラックスできるため、冷えの対策にもなることに加え、質のよい睡眠につながります。
とくに、下半身型や四肢末梢型のように手足が冷える方は、温度を37~39度のぬるめに設定することがポイントです。42度以上の熱めのお湯では交感神経が刺激されるのに対し、37~39度のぬるめのお湯では副交感神経が刺激され、自律神経を整えます。
| 体を温める食材を取り入れる

食事も、冷えを和らげるためには欠かせない要素です。とくに、肉・魚類がオススメです。
肉や魚は筋肉のもととなるたんぱく質が豊富に含まれており、冷えの原因である筋肉不足の解消に役立ちます。
またこれらの食材は、栄養学だけではなく薬膳などに代表される中医営養学的にも体を温めるのに役立つとされているのです。
中医営養学では体を温める食材を温・熱性といい、肉・魚のほかに以下のような食材があります。
かぶ
かぼちゃ
たまねぎ
にんにく
ねぎ
冷えが気になる方は、これらの食材を使った温かい料理がおすすめです。
| 運動によって筋肉量を増やす
冷えの原因である筋肉不足を解消するためには、運動も必要です。
先ほどたんぱく質は筋肉のもとになるとお伝えしましたが、筋肉をつけるためには運動を行った後にたんぱく質を摂ると効果的です。
そして、運動の内容は筋トレがオススメですよ。下半身は比較的大きな筋肉があるため、その筋肉を使うスクワットを取り入れてみましょう。
| ツボもオススメ

冷えに対しては、ツボを指圧するのもよいですよ。冷えによいとされるツボは以下の通りです。
三陰交(さんいんこう)
内くるぶしから指4本分上にある
太衡(たいしょう)
足の甲にあり、足の親指と人差し指の骨が交わる場所にある
(親指と人差し指の間をなぞっていって骨にぶつかる手前)
腎愈(じんゆ)
腰あたりの背骨から外側2~3センチほどにある
(腰に手をあてた際の親指の位置)
ツボを押す際はゆっくりと、気持ちいいと思える程度の力で押してみてください。
| どこを温めるとよいのか
足先の冷えが気になる場合は、足首にある太谿(たいけい)を温めるとよいですよ。
太谿は、足のくるぶしとアキレス腱の間にあるくぼみの部分にあります。
小さめのカイロを太谿にあてて温めると、よいでしょう。
| 靴下の重ね履きは要注意

下半身型や四肢末梢型で足先の冷えを感じる方は、厚手の靴下を2枚、3枚と重ね履きする場合もありますが、選ぶ靴下によっては逆効果の可能性もあります。
通気性の悪い素材の靴下を重ね履きすると、足が汗をかいてしまうことも。汗は本来、体を冷やすために分泌されるため、出てきた汗によってさらに足先が冷えてしまうのです。
できるだけ通気性がよく、蒸れにくい素材を選ぶとよいでしょう。
| 足だけ冷えるのは病気のサイン?
足だけ冷える方の中には、閉塞性動脈硬化症や急性動脈閉塞症といった病気が隠れている可能性もあります。
ただし、これらの病気は足の冷えだけでなくしびれといった他の症状もあらわれるため、足だけの冷えがあるからといってすぐに病気を疑う心配はありません。
一方で、昔から「冷えは万病のもと」とも言われています。冷えは未病であり、それがさまざまな病気のきっかけとなる可能性もあるのです。
病気を未然に防ぐためにも、気になる症状があったら一度医療機関を受診し、医師へ相談してみてはいかがでしょうか。
| まとめ
冷えは下半身型、四肢末梢型、内蔵型、全身型の4タイプに分けられ、その原因は以下のものが考えられます。
・痩せや筋肉量の低下
さらにこれらを解消する際には、漢方薬を取り入れるといった方法をご紹介しました。
漢方薬については症状に合わせて処方されるため、取り入れたい方は一度医療機関へ相談するとよいです。
それでは、当記事でご紹介した内容があなたの冷えの悩みに役立てるよう願っています。