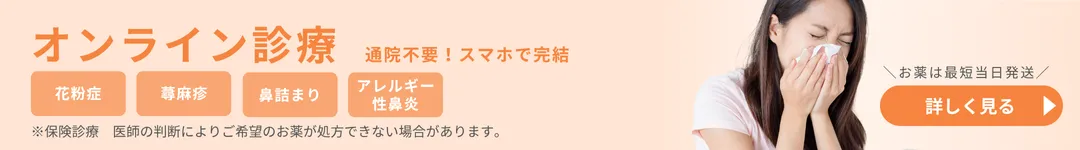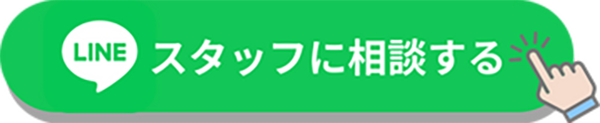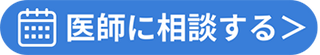日本人に花粉症が多いのはなぜ?予防・治療方法もあわせて解説
ホーム > ブログ


日本赤十字社医療センター、虎の門病院で産婦人科医として臨床経験を積む。「忙しく頑張っている人がもっと気楽に相談できる場所を作りたい」との想いを胸に、2024年11月、オンライン診療専門のシンクヘルスクリニックを開院。
内科、皮膚科、医療用漢方、婦人科など、受診者の悩みに幅広く対応。心のケアも大切に、一人ひとりが安心して自分の体と向き合えるようサポートしている。
目次
1 日本人に花粉症が多いのはなぜ?
1.1 スギの大量植林による花粉量の増加
1.2 大気汚染による影響
1.3 食生活の変化
2 花粉症は国民の2人に1人が発症している病気
2.1 花粉症の発症メカニズム
2.2 花粉症は戦後から増加し始めた
2.3 花粉症は2人に1人以上が発症している
2.4 花粉症の発症率が高い地域
3 海外と日本の花粉症対策の違い
4 花粉症の予防・治療方法
4.1 眼鏡やマスクで花粉を防ぐ
4.2 花粉が付着しにくい服装を選ぶ
4.3 うがいと洗顔を行う
4.4 換気を工夫し定期的に掃除を行う
4.5 病院で治療を受ける
4.5.1 薬物療法
4.5.2 アレルゲン免疫療法
4.5.3 手術
5 まとめ
日本人の花粉症患者数は年々増加傾向にあり、国民病ともいわれています。
日本人の2人に1人以上が発症しており、春先になると鼻水やくしゃみなどの花粉症の症状に悩まされる方が増えます。
この記事では、日本人に花粉症がなぜ多いのか、その理由について解説します。
花粉症の発症メカニズムや花粉症の予防・治療方法などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
| 日本人に花粉症が多いのはなぜ?

日本人に花粉症が多い理由として、以下の3つが挙げられます。
・大気汚染による影響
・食生活の変化
ここでは上記3つの理由についてそれぞれ解説します。
| スギの大量植林による花粉量の増加
日本人に花粉症が多い理由として、スギの大量植林による花粉量の増加が挙げられます。
花粉症を引き起こす花粉の種類は50種類以上ありますが、その中でも特に多く見られるのがスギやヒノキを原因とする花粉症です。
特にスギは花粉症の約70%を占めると言われています。
スギ花粉症が多い原因は、全国の森林の18%、国土の12%をスギ林が占めているためです。
(参照:「的確な花粉症の治療のために」厚生労働省)
スギの大量植林の主な原因は、戦中・戦後の物資不足や住宅建築に伴う用材需要の増大にあります。
これらの原因によって天然林を人工林に転換する必要が出てきたため、日本の固有樹種かつ加工しやすい特徴を持つスギが積極的に植えられるようになりました。
その結果、現在では森林の約4割が人工林となり、さらに人工林の約4割をスギが占めています。
(参照:「スギ・ヒノキ林に関するデータ」林野庁)
スギが増えると当然花粉の生産量も増えるため、花粉症に悩まされる人が増えてきているのです。
| 大気汚染による影響
日本人に花粉症が多い理由として、大気汚染による影響も考えられています。
大気中に浮遊する汚染物質と花粉が接触することで起こる作用が、花粉症の発症と深く関係していることが解明されているのです。
花粉症の発症原因は、花粉の表面に付着する『Cry j1』と花粉内部にある『Cry j2』というアレルゲン物質です。
このアレルゲン物質が花粉から分離し、人間の体内に入り込み、抗体と結合することにより花粉症を引き起こします。
そしてアレルゲン物質の分離をサポートしているのが、大気中に浮遊する汚染物質です。
具体的な汚染物質としては、黄砂や自動車排気ガス、ゴミ焼却場や工場排煙などから出る炭素物質があります。金属成分などが挙げられます。
通常、自然な状態であれば花粉が分離する確率は2割程度ですが、大気中の汚染物質と接触すると約8割が分離してしまうのです。
(参照:「花粉症と大気汚染の原因物質との関連性を化学的に解明」国立大学)
つまり通常よりもはるかに高い確率で割れやすくなるため、花粉がさらに拡散されやすくなり、花粉症患者が増える原因となっています。
| 食生活の変化
花粉症が増えてきている原因の一つとして、日本人の食生活の変化の影響も考えられています。
花粉症が増え始めてきた時期と、日本人の食生活が欧米化し始めてきた時期が一致するためです。
欧米式の食事が広まったことにより、動物性たんぱく質や脂肪の過剰摂取、食品添加物の増加といった変化が現れました。
食生活の欧米化によって腸内環境や血行が悪化すると、アレルギー体質を引き起こす可能性があるだけでなく、症状の悪化にも影響すると考えられています。
| 花粉症は国民の2人に1人が発症している病気
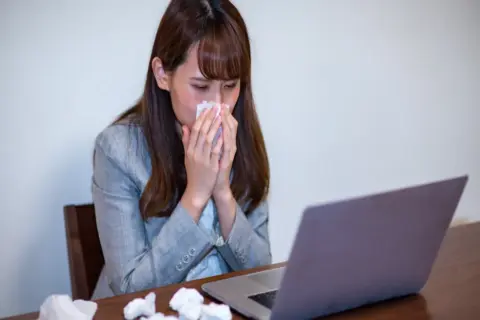
花粉症は国民の2人に1人が発症しており、いわば国民病ともいわれている病気です。
ここでは花粉症の発症メカニズムや日本人の花粉症発症率などについて解説します。
| 花粉症の発症メカニズム
花粉症は体内にアレルギー素因のある人のみが発症する病気です。
アレルギー素因を持っている人は花粉に対応するための抗体である『IgE抗体』を作り出し、アレルギー反応の準備が整った状態(感作の成立)になります。
感作が成立してもすぐに花粉症を発症するわけではなく、数年単位で花粉を浴び続け、抗体が十分に蓄積された時に花粉が体内に入ると、鼻水やくしゃみといった症状が現れます。
感作までの期間は個人差がありますが、花粉量の増加や体質の変化などの影響から、大人だけでなく小さな子供でも花粉症を発症するようになっています。
関連記事
喉がかゆいのは花粉症が原因?~症状や対処法・薬について解説~
| 花粉症は戦後から増加し始めた
花粉症は戦後から増加し始めた病気です。
戦中・戦後の資材不足によって多くの森林が伐採され荒廃した後、復興の一環として大規模な植林が行われ、日本各地でスギが大量に植えられるようになりました。
スギは加工しやすく建築や家具などの幅広い用途に利用できるため、積極的に植えられたのです。
またスギが花粉を本格的に飛散させるのは植林から20年ほど経過したころとされており、戦後に植えられたスギ林が成長するにつれて、大量の花粉を産生するようになりました。
このような原因によって花粉症を発症する人が増え、現在のように国民の多くが悩まされる病気となったのです。
| 花粉症は2人に1人以上が発症している
花粉症の正確な患者数はわかっていませんが、2人に1人以上が発症している病気といわれています。
全国の耳鼻咽喉科医とその家族を対象にした鼻アレルギーの全国調査では、以下のように花粉症の患者数が推移していることがわかっています。
・1998年:19.6%
・2008年:29.8%
・2019年:42.5%
このデータを見てわかる通り、10年ごとに行われている調査でほぼ10%ずつ患者数が増加しています。
このことから、2019年から10年後の2029年には50%超にまで患者数が増えていることが予想されるでしょう。
さらに上記のうちスギ花粉症の患者数について調査したデータもあります。
・1998年:16.2%
・2008年:26.5%
・2019年:38.8%
花粉症にはスギやヒノキ、ブタクサなどさまざまな種類がありますが、花粉症の大半を占めるのがスギ花粉症ということがわかります。
また2019年に行われた全国疫学調査では、花粉症は10~50代の患者さんが全体の45%以上を占めていることも明らかになっています。
(参照:「花粉症環境保健マニュアル2022」環境省)
| 花粉症の発症率が高い地域
日本ではスギやヒノキの花粉量が圧倒的に多いため、これらの樹林が多い地域では花粉症の発症率が高まります。
スギは北海道南部から九州にかけて広い地域に植林されており、特に東北地方・九州地方で多いです。
東北から北陸にかけての地域は比較的少なく、東海地方から西にかけてまた多くなっています。
地方別のスギ林の面積(単位千ha)は以下の通りです。
| 1970年 | 2000年 | 2012年 | 2017年 | |
| 北海道 | 26 | 32 | 33 | 32 |
| 東北 | 794 | 1252 | 1250 | 1245 |
| 関東 | 332 | 354 | 345 | 343 |
| 北陸甲信越 | 305 | 462 | 461 | 458 |
| 東海 | 353 | 387 | 385 | 385 |
| 近畿 | 375 | 431 | 426 | 425 |
| 中国 | 324 | 326 | 324 | 322 |
| 四国 | 378 | 414 | 409 | 405 |
| 九州 | 736 | 871 | 803 | 821 |
| 全国 | 3554 | 4528 | 4475 | 4438 |
| 海外と日本の花粉症対策の違い

日本の花粉症はスギが主な原因植物となっていますが、海外では地中海地域はヒノキ、北欧地域はシラカンバ、北米地域はブタクサが主な原因です。
これらの地域では、短期的な対策・予防として人間の治療や予防、中長期的な対策として原因植物の除去や生活環境の整備が行われています。
日本では花粉症を社会問題として、政府が『発症等対策』『発生源対策』『飛散対策』の3つを柱に対策を行っています。
各対策の具体的な方法は以下の通りです。
| 花粉症対策の3本柱 | 具体的な対策方法 |
| 発症等対策 | ・対症療法(症状を抑えるための治療) ・アレルゲン免疫療法(花粉に触れても症状が出ないようにする治療) |
| 発生源対策 | 令和15年度(2033年度)までにスギ人工林を約2割減少させることを目標とした対策 ・スギ人工林の伐採、植替えの加速化 ・スギ材の需要拡大 ・花粉の少ない植木の生産拡大林業の生産性向上および林業労働力の確保 |
| 飛散対策 | 民間事業者が行うスギ花粉飛散量の予測精度向上の支援 |
一方、海外では花粉生産量の多い樹種の植栽の制限や、花粉飛散の原因となる樹林の刈り込み・駆除などが行われています。
そして海外には生活環境の整備を重視した花粉症対策もありますが、日本においてはまだ特別な取り組みは行われていません。
短期的な対策や長期的な対策は行われているものの、長期的な効果が現れるまでの中期的な対策が取られていないことが課題に挙げられます。
| 花粉症の予防・治療方法

花粉症を予防するための方法として、以下の4つが挙げられます。
・花粉が付着しにくい服装を選ぶ
・うがいと洗顔を行う
・換気を工夫し定期的に掃除を行う
ここでは上記4つの予防方法と合わせて、病院での花粉症の治療や対症療法も解説します。
| 眼鏡やマスクで花粉を防ぐ
花粉症を予防するためには、眼鏡やマスクなどで花粉を防ぐことが大切です。
花粉症用のマスクでは花粉が約1/6、花粉症用の眼鏡では1/3程度まで花粉量が減少することがわかっているため、ぜひ積極的に活用してみてください。
(参照:「花粉症に対する各種治療法に関する科学的根拠をふまえた評価研究」感覚器障害及び免疫・アレルギー等研究事業)
また花粉症用のものではなく、通常の眼鏡やマスクでも十分効果が期待できます。
マスクは横に隙間ができるとそこから花粉が入り込んでしまうため、できるだけ顔にフィットし、息がしやすいものを選びましょう。
特に目の症状がひどい方は、視力が悪くなくてもダテメガネなどを着用して対策することで、対策の一つになります。
| 花粉が付着しにくい服装を選ぶ
花粉症を予防するための方法として、花粉が付着しにくい服装を選ぶことも重要です。
一般的にウール製の衣類は綿や化繊に比べて花粉が付着しやすいため、なるべく避けた方が良いでしょう。
また花粉は人間の肌にも付着するため、花粉が飛散する時期はつばの広い帽子をかぶる、手袋を着用するなど服装にも注意してみてください。
| うがいと洗顔を行う
花粉症を予防するためには、うがいと洗顔をしっかり行うことが大切です。
花粉は肌や粘膜に付着するため、そのまま放置していると花粉症を発症したり症状が悪化したりする恐れがあります。
外から帰宅したらうがいと洗顔をすることを心がけ、花粉を落とすようにしましょう。
また髪の毛にも花粉が付着するため、毎日帰宅後シャワーを浴びることで、花粉を落としやすくなります。
| 換気を工夫し定期的に掃除を行う
花粉が飛散しやすい時期には、換気方法を工夫することが大切です。
花粉の飛散量が増える時期に窓を全開にして換気をすると、大量に花粉が室内に流入してしまいます。
換気をする際は窓を開ける幅を最小限にして、レースのカーテンをするようにしましょう。
またカーテンにも花粉が付着するため、定期的に洗濯・掃除をすることが大切です。
自宅に24時間換気システムが設置されている場合は、花粉に対応した給気口フィルターの使用も検討してみてください。
| 病院で治療を受ける
花粉症の症状でお悩みの場合は、病院で適切な治療や対症療法を受けましょう。
花粉症の治療や対症療法には以下の3つの方法があります。
・アレルゲン免疫療法
・手術
ここでは上記の治療や対症療法について簡単に解説します。
– 薬物療法
薬物療法は、薬によって花粉症の症状を緩和する対症療法です。
抗ヒスタミン薬や鼻噴霧用ステロイド薬などがあり、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状を改善できます。
また目の症状が現れている場合には、抗ヒスタミン点眼薬やステロイド点眼薬などが処方される場合もあります。
薬物療法は一時的に症状を和らげるためのもので、花粉症を完治させる方法ではないことは理解しておきましょう。
– アレルゲン免疫療法
アレルゲン免疫療法は、花粉の成分に体を慣れさせて、花粉に触れてもアレルギー反応が発生しないようにするための治療方法です。
薬を服用する『舌下免疫療法』と注射で投与する『皮下免疫療法』の2種類があります。
アレルゲン免疫療法は花粉の飛散していない時期に開始し、舌下免疫療法は最低でも3年間の服用が必要です。
医師に相談のうえで、治療開始時期を検討してみましょう。
– 手術
薬物療法が効かないなどの症状が重い患者さんの場合は、手術も選択肢の一つになります。
花粉症の手術方法には以下のようなものが挙げられます。
・鼻腔形態を整復して鼻通りを改善させる手術(粘膜下下鼻甲介切除術、鼻中隔矯正術など)
・鼻水を抑制させる手術(後鼻神経切断術など)
患者さんの症状に合わせて、医師の判断のもと治療方法が提案されます。
| まとめ
日本人に花粉症が多い理由は、スギの大量植林による花粉量の増加や大気汚染による影響、食生活の変化などです。
花粉症の患者数は年々増加傾向にあるため、現在症状がない方も油断せず、しっかりと対策を講じることが大切です。
当院では、花粉症のオンライン診療を行っています。
オンライン診療なら外出せずに薬が自宅まで届く(院内処方のみ)ため、花粉症の症状にお悩みで外出をなるべく控えたい方は、ぜひご相談ください。
参考文献
- 林野庁 森林・林業とスギ・ヒノキ花粉に関するQ&A:林野庁
- 政府広報オンライン 政府の花粉症対策
- 濱田 聡子 アレルギー性鼻炎における手術療法の実際と位置付け
- 厚生労働省 花粉症の原因 花粉症予防行動に関する普及啓発について はじめに ~花粉症の疫学と治療そしてセルフケア~ スギ花粉症について日常生活でできること
- 環境省 花粉症環境保健 マニュアル 2022
- 大森 玲子 花粉症に及ぼす生活習慣の影響について
- 花粉症と大気汚染の原因物質との関連性を化学的に解明|環境への取り組み
- 花粉症に関する関係閣僚会議決定 花粉症対策の全体像
- 河瀬麻里 海外の花粉症対策と比較した日本の花粉症対策の特性