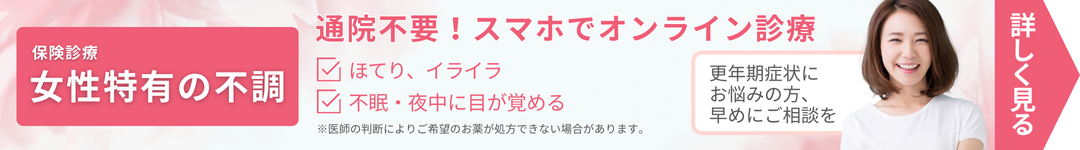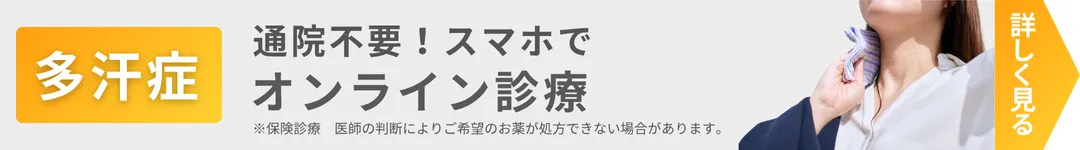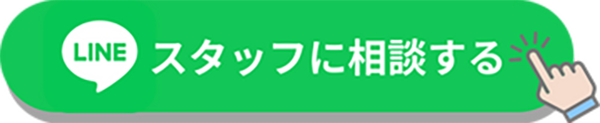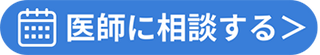汗をかきやすい人の特徴と病気のサイン|セルフチェックで悪い汗を確認
ホーム > ブログ


日本赤十字社医療センター、虎の門病院で産婦人科医として臨床経験を積む。「忙しく頑張っている人がもっと気楽に相談できる場所を作りたい」との想いを胸に、2024年11月、オンライン診療専門のシンクヘルスクリニックを開院。
内科、皮膚科、医療用漢方、婦人科など、受診者の悩みに幅広く対応。心のケアも大切に、一人ひとりが安心して自分の体と向き合えるようサポートしている。
目次
1 汗をかきやすい人の特徴と原因(ちょっと動くと汗が出るのはなぜ?)
1.1 正常な発汗のメカニズム
1.1.1 体温調節のための汗
1.1.2 精神的な刺激による汗
1.1.3 味覚の刺激による汗
2 汗と病気の関係|多汗症・更年期・甲状腺など
3 セルフチェック~汗の多さは体質?病気?~
4 結果を解説
4.1 体質や環境の要因
4.1.1 代謝が良い
4.1.2 不安や緊張を感じやすい
4.1.3 太っている
4.1.4 家族に汗っかきの人がいる
4.2 更年期障害
4.3 原発性局所多汗症
4.4 糖尿病
4.5 自律神経失調症
4.6 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
4.7 早めの受診が必要な危険な汗
5 汗をかきやすい人ができるセルフ対策
5.1 バランスのよい食事
5.2 刺激物・嗜好品を摂り過ぎない
5.3 ストレスを溜めない
5.4 運動・入浴で汗をかく
6 当院でできる治療
7 まとめ
「ちょっと動くと汗が出る…」服の汗染みやにおいなど、汗に関するお悩みは人目も気になりますよね。
ちょっと動くだけで汗が出るのは、体質だけでなく、病気が隠れている場合もあります。
セルフチェックで、汗が多くなる理由を探ってみましょう。
不快な汗を少しでもコントロールしやすくする生活習慣のポイントもまとめました。
どうぞ最後までお付き合いください。
| 汗をかきやすい人の特徴と原因(ちょっと動くと汗が出るのはなぜ?)

「ちょっと動いただけなのに、汗が出る…」「人よりも汗をかきやすい気がする」という方は、体質または病気の可能性があります。
汗がつくられる汗腺(エクリン汗腺)は、全身に200万〜500万個ほどありますが、すべての汗腺が汗を出しているわけではありません。乳幼児期に”使われる汗腺”が環境の影響などで徐々に決まり、その後の発汗傾向に影響します。
活動している汗腺の数が多い人は、汗をかきやすい体質といえるかもしれません。
また、汗をかくのは人間の自然な生理現象であり、正常な働きですが、時に体の異常を知らせるサインにもなります。
「汗は正常な反応」と思い込んでしまうと、体からのサインを見逃してしまうかもしれません。悪い汗ではないか、確認するのも大切です。
| 正常な発汗のメカニズム
よい汗と悪い汗を見分ける上でも、汗の基本的な役割を知っておきましょう。
汗の主な役割は、体温を一定に保つことです。さらに皮膚をうるおわせたり、細菌やウイルスから体を守る役割も持っているといわれています。
– 体温調節のための汗
体温が上昇した際、体の水分を汗として体外に出し、蒸発する際に熱を奪うことで体温を一定に保つ働きをしています。夏の暑い日に汗をかくことや、運動したことによる汗は、体温調節のための汗です。
– 精神的な刺激による汗
緊張や不安、焦りなど精神的ストレスを受けたときにかく汗もあります。「手に汗を握る」「冷や汗」といった言葉がまさにその状態を示していますね。
精神的な刺激による汗は、手のひらや足の裏、脇などにかきやすいとされています。
– 味覚の刺激による汗
辛いものを食べると汗が止まらなくなる、という方は多いのではないでしょうか。
辛み成分のカプサイシンが温度を感知するセンサーを刺激して起こります。味覚の刺激による汗は、主に顔や頭に出やすい傾向にあります。
| 汗と病気の関係|多汗症・更年期・甲状腺など

病気のサインの1つとして、汗の出方に変化が出る場合もあります。
たとえば
・更年期障害
・多汗症
・糖尿病
・自律神経失調症
・甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
などが、発汗に影響を与えやすい疾患です。
症状の出方には個人差がありますので、汗以外の症状が出ていないかなど他の自覚症状に着目するのも大切です。
| セルフチェック~汗の多さは体質?病気?
汗でお悩みの方は、以下のセルフチェックで、汗の多さの理由を探ってみましょう。
結果はあくまで参考とし、気になる症状は医療機関にご相談ください。
| 結果を解説

セルフチェックの結果はいかがでしたか?ご自身の結果と関連する解説をぜひ確認してみましょう。
| 体質や環境の要因
汗が出やすい体質と関連する要因をまとめました。体質とはいえ、汗が多くて悩んでいたり、生活に支障がある場合には、治療の対象となる場合もあります。
1人で悩まず、ご相談ください。
- 代謝が良い
代謝が良い人は、体の中で熱をたくさん生成し、体温が高めになる傾向があります。体温を一定に保つために、汗をかきやすくなるので、少し動いただけでも汗が出ることがあります。
しかし、代謝が悪い人の中にも、汗をたくさんかく人はいますので、代謝の良し悪しだけが関係しているわけではないのです。
- 不安や緊張を感じやすい
上記の通り、精神的ストレスへの反応として汗をかくので、普段から不安や緊張を感じやすい人は、人よりも汗をかきやすいといえるかもしれません。
不安や緊張を感じるのは、自分を守るための正常な反応ですが、過剰となると、日常生活への影響が出ることもあります。
また、汗が人より多いことを不安に思ったり、恥ずかしいと思うことで、さらに汗が止まらなくなるという悪循環が生じる場合もあるのです。
受診が必要かどうかわからない、迷っているという方へ、診察よりも気軽なLINE相談もありますよ。
- 太っている
皮膚の下にある皮下脂肪は熱が伝わりにくい性質を持っているため、肥満傾向にある人は体内に熱がこもりやすいと考えられます。体温を保つために、何とか熱を発散しようとすると、汗の量が多くなってしまうのです。
もし体重や血液検査などの項目について、健診で要経過観察と指摘されている場合には、汗のお悩みと同時に、一度医療機関で相談してみてはいかがでしょうか。
関連記事
生活習慣病の種類一覧!予防と備えを詳しく解説
生活習慣病とはどんな病気?種類や原因・予防法も解説
- 家族に汗っかきの人がいる
汗をかきやすいという特徴は、遺伝する傾向があるといわれています。そのため、家族に汗っかきの人がいる場合には、遺伝的な体質として、ご自身も汗っかきであるのかもしれません。
「こんなこと病院で相談していいの?」「何科にいけばいい?」と迷うときは、LINE相談でサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。
| 更年期障害
女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が減るのに伴い、心身にさまざまな変化が起きる更年期。
40~50歳代の女性のうち、30~40%の人が更年期障害の可能性があるという結果があります。(※)
一方で、更年期症状を感じている人のうち、医療機関を受診していないケースも多く含まれます。
更年期の代表的な症状のひとつとして、のぼせ、ほてり(ホットフラッシュ)や発汗があります。汗については、とくに寝ているときに気になる方が多いようです。
更年期の年代に該当する女性で、汗が気になる方は、更年期障害の可能性も考慮していく必要があります。
更年期症状かもしれない、とお悩みの方は医療機関に相談し、必要に応じた治療を受けることで症状が改善する可能性が高いです。
当院では婦人科医師による更年期治療に対応しておりますので、ご相談のみの方もお気軽にご利用ください。
(※)厚生労働省(2022).「更年期症状・障害に関する意識調査」 基本集計結果
関連記事
更年期のセルフチェック〜早めの対策で快適な毎日を過ごそう〜
| 原発性局所多汗症
日常生活に支障をきたすほど、大量の汗をかいてしまう状態であり、以下のような基準に当てはまると、多汗症である可能性が考えられます。
・25歳以下に発症している
・左右対象に汗が出る
・睡眠中は汗が止まる
・週1回以上、汗が気になる状態が続いている
・家族にも汗で悩む人がいる
・症状によって、日常生活に支障が出ている
※過剰な発汗が6か月以上続き、上記2項目以上が当てはまる場合
症状の重症度には段階があり、汗で湿っているレベルから、汗の水滴が滴り落ちるほどにもなります。
また、過剰な発汗を「周りから不快に思われているのではないか」と気にする毎日に精神的苦痛を抱くことも多いのです。
身体的疾患がなく、発汗の原因がはっきりわからない場合は「原発性多汗症」と分類されます。
また、汗が多く出ている場所が全身なのか、体の一部分なのかによって全身性多汗症・局所性多汗症と分類され、治療薬の選択も変わります。
局所性多汗症で汗が多く出る部位は
・脇
・手のひら
・足の裏
・頭、顔
に分類され、複数の部位に症状が見られる場合もあります。
「汗っかきな体質」と見過ごしやすい多汗症ですが、治療の選択肢があり、症状を和らげられるかもしれません。汗の悩みが気になる場合は、一度皮膚科で相談してみましょう。
関連記事
皮膚科のオンライン診療は保険適用される?処方される薬や料金について解説
| 糖尿病
糖尿病によって高血糖の状態が続くと、神経へのダメージが生じ、合併症を招く場合があります(糖尿病性神経障害)。
汗をコントロールする神経にダメージがあると、汗が多くなったり、逆に汗を全くかかなくなったりという異常が起きる場合があるのです。
糖尿病の初期は自覚症状が出にくいといわれていますが、汗のかき方が急に変わるなどの変化を感じたときは、注意してみましょう。喉の渇き、倦怠感、目のかすみ、皮膚のかゆみ、頻尿なども、糖尿病のサインの1つです。
もしすでに糖尿病で内服薬やインスリン注射による治療を受けている中で、冷や汗を感じることがあったら、低血糖の可能性もあります。
低血糖は、長時間食事がとれず、お腹が空いていたり、食事量が少なかったり、運動をした後などに、血中のブドウ糖が少なくなりすぎることで起こりやすいのです。
・冷や汗
・手の震え
・動悸
・熱感
・不安感
・悪心
などの症状が出始めたら、糖分を摂取するなど、医師から指示されている対応を早めに実行するようにしましょう。
当院では糖尿病の診療も行っています。「この汗って糖尿病なの?」と心配な気持ち、1人で抱えずに相談してみませんか。
| 自律神経失調症
汗の調節をする汗腺の働きは自律神経が担っています。自律神経は自分の意思とは関係なく、体内のバランスを保つためのさまざまな働きを支える神経です。
この自律神経のバランスが崩れてしまう状態を、自律神経失調症といいます。
症状は人によって多様で、その人の体の弱い部分に現れやすいといわれています。
汗の異常のほかにも、以下のような症状が出ていませんか?
・疲労感、倦怠感
・しびれ
・息切れ、動機
・めまい、頭痛
・不眠、寝汗
・食欲不振
・肩こり、背中や腰の痛み
・腹痛、下痢、便秘
自律神経失調症の原因ははっきりしないものの、ストレスや生活習慣の乱れが関係しているとされています。ご自身の生活に心当たりがないか、振り返ってみましょう。
また、上記のような不調がある場合、内科を受診して他の病気の可能性がないかをよく調べることも大切です。とくに辛い症状があるときは、それに合わせて診療科を選ぶという方法もあります。
| 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
甲状腺で甲状腺ホルモンが過剰にされてしまうバセドウ病(甲状腺機能亢進症)でも、発汗の異常が起こる場合があります。
バセドウ病は甲状腺ホルモンの過剰分泌によって、新陳代謝が活発になるため、汗が多くなる場合があります。その他にも、脈拍数の増加、体重の減少、動悸、手の震え、イライラ、眼球突出などの症状が出る人もいるのです。
甲状腺ホルモンの検査は血液検査で行われ、甲状腺の腫れなどを超音波検査で検査する場合もあります。
気になる症状があり、検査を受けてみたいと思われるかたは、内分泌科など、甲状腺を専門にしている医療機関に相談してみましょう。
| 早めの受診が必要な危険な汗
汗の異常に加えて
・発熱
・体重減少
・寝汗で目が覚める
・首や脇のリンパ節が腫れている
などの症状がある場合には、注意が必要です。免疫に関わる病気や感染症が隠れていることもあります。
ただし、これだけの症状でなにか大きな病気があるとは判断できません。
大切なのは「いつもと違う」「症状が長く続く」と思ったときに、早めに病院で相談することです。
| 汗をかきやすい人ができるセルフ対策

ご自身でできる汗の対策もあります。どれも特別な対策ではありませんが、日々の習慣の積み重ねが、体内のバランスを作り出しているといえるかもしれません。
| バランスのよい食事
自律神経を整える上でも、バランスのよい食事を摂るのは大切です。また、汗をかくと、水分や塩分(ナトリウム)やマグネシウム、亜鉛、カリウム、ビタミン(B1、B2、B6、B12、C他)なども失われてしまいます。
汗対策に、特定の食べ物だけを食べるのは、栄養バランスの面から見るとむしろ逆効果となる場合があります。
丼ものや麺類のみなど、摂取する品目が少なくなりがちなメニューには、副菜をプラスするなどの工夫をぜひ取り入れてみましょう。
| 刺激物・嗜好品を摂り過ぎない
とくに辛いものや酸っぱいものは、発汗を促してしまいますので、汗を気にしているときには控えるようにしましょう。
また、コーヒーや緑茶など、カフェインを多く含む飲み物や、アルコール、タバコといった嗜好品も、交感神経を優位にします。摂りすぎて自律神経の乱れにつながらないように気をつけましょう。
| ストレスを溜めない
ストレスは自律神経に影響を与え、バランスを崩すきっかけにもなります。受けるストレスをゼロにするのは難しいですが、ご自身にとってストレス解消となるものを見つけ、ストレスとうまく付き合っていけるとよいですね。
また、ストレスの心身への影響は個人差がありますが、寝つきが悪くなるなど、睡眠への影響は出る方も多いようです。ついお酒などに頼っているという方は、一度医療機関に相談してみるとよいでしょう。
関連記事
寝つきが悪いのはなぜ?~対処法と寝つけないときの過ごし方まで~
| 運動・入浴で汗をかく
汗が気になるからといって、運動や入浴を控える必要はありません。
むしろ、運動不足は多汗症を悪化させてしまう可能性もあります。運動して適度な汗をかくと、汗腺の機能を正常に保つのにつながりますよ。激しい運動は避け、ウォーキングなどの軽い運動から始めてみましょう。
また、入浴の際は熱すぎるお湯を避け、肩までしっかりお湯につかるようにしましょう。時間をかけて半身浴をしたり、ひざ下と手をお湯につける手足浴もよいといわれています。
そして、ゆっくりと入浴すると、汗腺の機能によい影響が期待できるだけでなく、リラックスにもつながります。
| 当院でできる治療
当院ではオンライン診療で
・更年期障害:漢方、ホルモン補充療法、サプリ(エクエル)
・多汗症:外用抗コリン薬(エクロックゲル、ラピフォーラピフォートワイプ、アポハイドローション)
・かかりつけのある糖尿病の方の内服薬 継続処方
などに対応しています。万が一、他の病気の可能性が疑われる場合には、医師が対面診療をご案内しますので、安心してご相談ください。
| まとめ
汗は体温調節や体を守るための自然な働きですが、時には病気のサインになっていることもあります。
「体質だから」と思い込んでしまうと、治療が必要な状態を見逃してしまう可能性もあります。
本記事でご紹介したセルフチェックや生活習慣の工夫は、あくまで目安です。汗が日常生活に支障をきたしていたり、「いつもと違う汗」に不安を感じたら、早めに医師へ相談することが安心につながります。
当院ではオンライン診療により、更年期障害・多汗症・糖尿病などの治療やご相談に対応しています。気になる汗について「これって大丈夫?」と思ったら、お気軽にご相談ください。