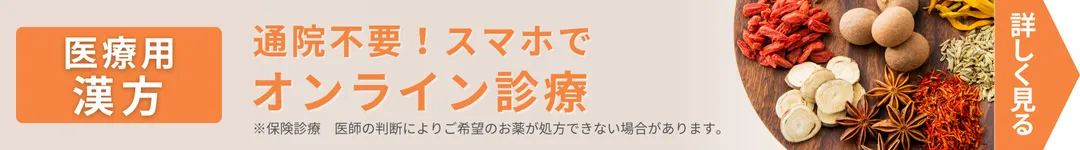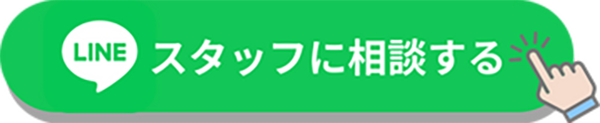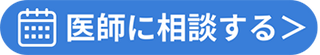風邪の鼻水・咳・喉の痛み…漢方なら体質に合わせて症状を緩和!
ホーム > ブログ


日本赤十字社医療センター、虎の門病院で産婦人科医として臨床経験を積む。「忙しく頑張っている人がもっと気楽に相談できる場所を作りたい」との想いを胸に、2024年11月、オンライン診療専門のシンクヘルスクリニックを開院。
内科、皮膚科、医療用漢方、婦人科など、受診者の悩みに幅広く対応。心のケアも大切に、一人ひとりが安心して自分の体と向き合えるようサポートしている。
1 あなたの風邪はどのタイプ?
1.1 喉の痛みや声枯れをやさしくケアする漢方
1.1.1 桔梗湯(体力がある、喉の痛みが強い、痰の切れが悪い)
1.2 鼻づまりで集中できないときの漢方アプローチ
1.2.1 葛根湯(体力に自信がある、寒気・発熱・首や背中のこわばり)
1.2.2 麻黄湯(体力に自信がある、悪寒・発熱・頭痛、汗をかいていない)
1.2.3 小青竜湯(体力がある、冷え性、薄く水っぽい痰、鼻水、くしゃみ)
1.3 軽い咳が続く方に寄り添う漢方
1.3.1. 麦門冬湯(体力が低下気味、乾いた咳、痰が少ない、口の乾き)
1.3.2 小青竜湯(体力がある、冷え性、薄く水っぽい痰、鼻水、くしゃみ)
1.4 悪寒や冷えには体の中から温める漢方を
1.4.1 葛根湯(体力に自信がある、寒気・発熱・首や背中のこわばり)
1.4.2 麻黄湯(体力に自信がある、悪寒・発熱・頭痛、汗をかいていない)
1.5 インフルエンザの初期にも漢方が使える
1.5.1 麻黄湯(体力に自信がある、悪寒・発熱・頭痛、汗をかいていない)
1.5.2 小柴胡湯(体力がある、寒気と熱が交互に来る、食欲不振、疲労感)
1.6 番外編:毎年つらい花粉症は漢方で体質改善を
1.6.1 小青竜湯(体力がある、冷え性、薄く水っぽい痰、鼻水、くしゃみ)
1.6.2 辛夷清肺湯(体力に自信がある、体に熱がこもっている、慢性的な鼻づまり・嗅覚障害)
2 効果的な漢方の使い方
3 自分に合った漢方、どう選ぶ?
4 まとめ
「なんか風邪っぽいかも?」と感じるとき、どんな症状から始まることが多いでしょうか。喉の痛み、鼻水、咳、など、いつも悩まされている症状が同じ場合、体質が関係しているかもしれません。
漢方薬は、特定の症状を抑えるだけでなく、体の全体の調子を整えてくれます。体質や症状に合った漢方薬を見つけるのに役立つ情報をまとめました。
| あなたの風邪はどのタイプ?

漢方医学では、『気・血・水(き・けつ・すい)』のバランスが崩れると、体調不良が起こるとされています。また、漢方薬は体質(証)に基づいて取り入れることで、より効果を発揮します。
風邪の初期症状が出やすい場所も人によって異なるため、その症状と体質に合わせた漢方薬を選べば、症状緩和が期待できるでしょう。
お悩みの症状をケアする漢方薬について、まとめました。
関連記事
漢方で体質改善!気血水の乱れにより起こる症状と体質に適した医療用漢方薬を解説
西洋薬と漢方薬の違いとは?それぞれの向いている病気や選び方について解説
| 喉の痛みや声枯れをやさしくケアする漢方
喉の腫れや痛み、炎症によって声が枯れてしまうと、会話などのコミュニケーションにも支障を来すため、できるだけ早く症状を緩和したいですよね。
– 桔梗湯(体力がある、喉の痛みが強い、痰の切れが悪い)
喉の症状がつらい方に適しているのが、桔梗湯(ききょうとう)です。痰を出しやすくする桔梗(ききょう)と炎症を抑える作用がある甘草(かんぞう)が配合されています。
漢方薬は一般的に、西洋薬に比べると効果が感じられるまでに時間がかかる場合が多いですが、桔梗湯は漢方薬の中でも、比較的早く効果を感じることがあります。
喉に直接作用するため、薬をお湯に溶かしてうがいをしながら飲むように指示されることもあります。
漢方薬の飲み方に迷う方は、医師と相談し、より適した方法を取り入れてみましょう。
| 鼻づまりで集中できないときの漢方
鼻づまりの原因はウイルスや細菌、アレルギー、気候の変化など、さまざまな要素が関係している可能性があります。鼻づまりが続くと、呼吸がしづらく眠りの質にも影響を与えてしまうことも。
漢方学では、体が冷えて水(すい)が溜まり、血行が悪くなると鼻の通りが悪くなると考えます。体を温める作用がある以下のような漢方薬が選択肢となるでしょう。
– 葛根湯(体力に自信がある、寒気・発熱・首や背中のこわばり)
風邪のひきはじめといえば葛根湯(かっこんとう)です。体を温め、血流をよくすることで、鼻の通りもよくなると期待できます。首や肩のこりを改善する作用もありますので、作業時の集中力回復も助けてくれるでしょう。
– 麻黄湯(体力に自信がある、悪寒・発熱・頭痛、汗をかいていない)
麻黄湯(まおうとう)はより強い鼻づまりがある方に適しています。葛根湯よりも体を温める作用のある生薬が配合されているため、症状にしっかり働きかけてくれる漢方薬です。
一方で、麻黄湯は体力があまりない方や汗をかきやすい方には向いていません。また、高血圧、心臓の病気、前立腺肥大がある方にはおすすめできません。体質と合っているかどうか、医師と相談するのがよいでしょう。
– 小青竜湯(体力がある、冷え性、薄く水っぽい痰、鼻水、くしゃみ)
鼻づまりの他にも、サラサラとした鼻水、くしゃみなどが続く場合には小青竜湯(しょうせいりゅうとう)があります。体を温めつつも、体の余分な水分を調整してくれるのが特徴です。眠気を誘う成分が入っていないため、薬の副作用で眠くなるのを避けたい方にも向いているでしょう。
鼻水の状態や、体力、冷えの程度などを医師と相談すると、より症状に合った漢方を選べますよ。
| 軽い咳が続く方に寄り添う漢方
咳はウイルスや花粉などの異物が体内に入ったときや、気道に溜まった痰などを、体外に出すために大切な体の働きです。
しかし、咳が長く続くと体力を消耗したり、喉を痛めてしまう場合もあるため、ケアが必要です。
– 麦門冬湯(体力が低下気味、乾いた咳、痰が少ない、口の乾き)
喉が乾燥している、痰が切れにくいという方向けには、麦門冬湯(ばくもんどうとう)という漢方があります。喉を潤し、咳を和らげてくれる作用があります。コンコンという空咳が続いているときに役立つでしょう。
– 小青竜湯(体力がある、冷え性、薄く水っぽい痰、鼻水、くしゃみ)
また、咳と同時に痰が出る場合には小青竜湯(しょうせいりゅうとう)が選ばれます。水分の偏りを整えてくれますので、鼻水・鼻づまりが同時にある方にも適しているでしょう。
同じ咳でも、乾いたタイプか、痰が多いタイプかで合う漢方が変わります。市販の薬で症状が改善しない場合には、自分の体質や症状に合った漢方はどれか、医師と相談してみましょう。
| 悪寒や冷えには体の中から温める漢方を
風邪のひきはじめに「ぞくぞくする」と感じるのは、体がウイルスなどと戦い始めたサインです。
体温を上げて免疫を働かせようとするとき、人は血管をぎゅっと縮め、筋肉を震わせて熱をつくり出します。このときに感じるのが、いわゆる悪寒です。
一方で、血流が体の表面に行き渡りにくくなるため、手足が冷えていると感じる方もいます。
つまり悪寒や冷えは、体が自ら熱を生み出し、防御態勢をとっている反応なのです。
– 葛根湯(体力に自信がある、寒気・発熱・首や背中のこわばり)
葛根湯(かっこんとう)は風邪の初期に、ぞくぞくするような悪寒があるときに使われる、代表的な漢方薬です。まだ熱が出ていない、もしくは熱が高くない段階で使われることが多いです。
– 麻黄湯(体力に自信がある、悪寒・発熱・頭痛、汗をかいていない)
麻黄湯(まおうとう)も葛根湯と同じく、風邪の初期に使われます。悪寒が強く震えていたり、汗が出ていない状態のときに使うのがよいでしょう。体を温め、発汗を促してくれます。
医師が処方する医療用漢方は、市販の漢方薬に比べて、有効成分の配合量が多い場合があります。悪寒など、風邪の初期症状が出ている場合は、早めに受診することで、こじらせるのを防げるかもしれません。
関連記事
冷えを緩和する漢方薬とは?~原因や温めるとよい部位を紹介~
| インフルエンザの初期にも漢方が使える
インフルエンザというと、抗インフルエンザ薬を思い浮かべる方も多いでしょう。重症化のリスクが高い場合などは西洋薬が選択されることが多くなります。
一方で、漢方薬にもインフルエンザの初期に使える処方があります。体を温めて発汗を促したり、長引く熱を調整するなど、体の回復を助けてくれるので、状況によっては漢方薬も選択肢の1つですよ。
– 麻黄湯(体力に自信がある、悪寒・発熱・頭痛、汗をかいていない)
体を温め、発汗を促す作用が強い麻黄湯(まおうとう)は、ウイルスに対抗するために、体が熱を高めている状態をサポートしてくれます。
しかし、すでに発熱で汗をかいている状態では、体力を消耗してしまう可能性もあるため、体調をよく見極めて服用することが大切です。
– 小柴胡湯(体力がある、寒気と熱が交互に来る、食欲不振、疲労感)
熱が何日も続くと、怠さや疲労感、胃腸の不調が現れる場合があります。そうした症状には小柴胡湯(しょうさいことう)が適しているでしょう。ウイルスによる炎症を抑えるだけでなく、弱っている体の機能回復を助けてくれます。
小規模な研究ではありますが、インフルエンザによる発熱の持続時間や総合的な症状について、麻黄湯は抗インフルエンザ薬と近い効果が得られたという研究もあります。(※)
どちらが適しているかは、体質や症状などさまざまな要因から判断されますので、医師とよく相談してみましょう。
| 番外編:毎年つらい花粉症は漢方で体質改善を
「今年も花粉の季節か…」と花粉症のシーズン前に憂うつな気分になる方も多いでしょう。花粉症に対して一般的によく処方される抗ヒスタミン薬は、くしゃみ、鼻水、鼻づまりをすばやく緩和してくれるのがメリットです。一方で、眠気やだるさといった副作用が気になることもあります。
そこで注目されているのが漢方による花粉症ケアです。漢方は体質や症状の現れ方に合わせて処方されます。単に鼻水を止めるのではなく、体全体のバランスを整えることで症状を和らげられますよ。
– 小青竜湯(体力がある、冷え性、薄く水っぽい痰、鼻水、くしゃみ)
小青竜湯(しょうせいりゅうとう)は透明でサラサラとした鼻水が出たり、くしゃみが出るタイプの方に向いています。体を温める作用もありますので、日頃から冷えが気になるという場合にも適しているでしょう。
– 辛夷清肺湯(体力に自信がある、体に熱がこもっている、慢性的な鼻づまり・嗅覚障害)
「鼻づまりが強く、頭が重い」「匂いを感じにくい」という場合には辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)が選ばれます。鼻の通りをよくする作用があり、粘り気のある鼻水が出る場合にも用いられる漢方薬です。
即効性のある西洋薬か、体質から整える漢方薬か、どちらが適しているか、副作用の出やすさやライフスタイルなどによっても異なります。医療機関で相談してみると、広い選択肢の中から、適した薬を見つけられることでしょう。
関連記事
風邪と花粉症の見分け方は?受診すべき診療科や治療・予防方法について解説
日本人に花粉症が多いのはなぜ?予防・治療方法もあわせて解説
| 効果的な漢方の使い方

漢方は「飲めばすぐ効く薬」というよりも、体質や不調を少しずつ整えていくものです。そのため、正しく続けることが大切になります。
ただし、すべての漢方が「ゆっくり効く」わけではありません。たとえば風邪のように急な症状には、発症のごく初期に服用すると効果を実感しやすいものもあります。一方で冷え性や体質改善など慢性的な不調に対しては、数週間から数か月と、ある程度の期間継続して飲むことで変化を感じられることが多いです。
また、漢方は食前や食間(食事の2時間後など)に服用するのが基本となります。これは、胃が空っぽのときに飲むことで吸収されやすいからです。
このように、漢方は種類によって効果の出方が変わるため、自己判断で使うよりも医師や薬剤師に相談して正しく続けることが大切です。
関連記事
漢方が合わないときの症状は?副作用が出やすい人の特徴や原因について解説
| 自分に合った漢方、どう選ぶ?

同じ「咳」という症状でも、人によって合う漢方は異なります。これは漢方には「証(しょう)」という考え方があるからです。
証とは、体質や症状の出方を総合的に判断した「あなたに合った漢方を選ぶための目安」のことです。たとえば、冷えが強いタイプか、のぼせやすいタイプか、疲れやすいタイプかなどで、選ばれる処方が違ってきます。
そのため、市販の漢方を自己判断で試すと「思ったほど効かない」と感じてしまうことも少なくありません。
医師に相談すると、あなたの体質や不調に合わせて適切な漢方を選んでもらえるだけでなく、必要であれば保険診療として処方を受けられることもあります。
「自分に合った漢方を知りたい」「長年の不調を体質から改善したい」と思ったときは、一度医師に相談してみてください。
悩んでいる症状があるけれど、「どの診療科を選べばいいのか分からない…」という方に、当院ではLINEでのサポートも行っていますよ。
| まとめ
風邪やインフルエンザ、花粉症といった症状は、誰にでも起こりうる身近な不調です。同じ「鼻づまり」や「咳」でも、人によって症状の現れ方や感じ方は異なり、漢方ではこうした違いを「証(体質)」として捉えます。
漢方薬の特徴は、症状を和らげるだけでなく、身体全体のバランスを整えること。
ただし、誰にでも同じように効くわけではなく、体質や体力によって適した処方は変わります。「自分に合うのはどの漢方か」を見極めるためには、医師に相談するのが安心です。
気になる症状があるときは、そのまま我慢せずに、あなたの体質に合った方法を一緒に探してみませんか?
忙しくてなかなか病院にいけない方も、スマホやパソコンからスキマ時間に受診可能なオンライン診療で、一度相談してみてはいかがでしょうか。