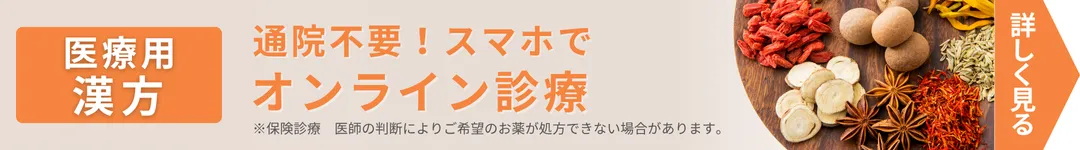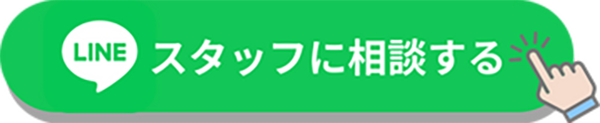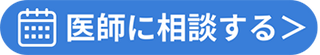西洋薬と漢方薬の違いとは?それぞれの向いている病気や選び方について解説
ホーム > ブログ


日本赤十字社医療センター、虎の門病院で産婦人科医として臨床経験を積む。「忙しく頑張っている人がもっと気楽に相談できる場所を作りたい」との想いを胸に、2024年11月、オンライン診療専門のシンクヘルスクリニックを開院。
内科、皮膚科、医療用漢方、婦人科など、受診者の悩みに幅広く対応。心のケアも大切に、一人ひとりが安心して自分の体と向き合えるようサポートしている。
目次
1 西洋薬と漢方薬の違いとは?
1.1 西洋薬は西洋医学に基づいて処方される薬
1.2 漢方薬は漢方医学に基づいて処方される薬
2 西洋薬と漢方薬のそれぞれ向いている病気
2.1 西洋薬の向いている病気
2.2 漢方薬の向いている病気
3 西洋薬と漢方薬どちらを選ぶべき?
3.1 西洋薬のメリット・デメリット・適しているケース
3.1.1 西洋薬のメリット
3.1.2 西洋薬のデメリット
3.1.3 西洋薬が適しているケース
3.2 漢方薬のメリット・デメリット・適しているケース
3.2.1 漢方薬のメリット
3.2.2 漢方薬のデメリット
3.2.3 漢方薬が適しているケース
4 漢方薬と西洋薬の併用は可能?
5 まとめ
体調不良になった際に服用する薬は、大きく分けて西洋薬と漢方薬の2種類あります。
最近では、漢方薬を処方する医療機関も増えています。西洋薬と漢方薬、それぞれの違いについて気になる方も多いでしょう。
この記事では、西洋薬と漢方薬の違いについて詳しく解説します。
西洋薬と漢方薬それぞれの向いている病気やメリット・デメリット、併用しても良いかなどもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
| 西洋薬と漢方薬の違いとは?

西洋薬と漢方薬の違いを簡単に説明すると、以下の通りです。
・西洋薬:西洋医学に基づいて処方される薬
・漢方薬:漢方医学に基づいて処方される薬
このほかにも化学的構成や治療の考え方などに違いがあります。
ここではそれぞれの特徴・違いについて解説します。
| 西洋薬は西洋医学に基づいて処方される薬
西洋薬は、特定の病気や症状に直接作用する有効成分を中心に設計された薬です。
単一の有効成分を持つ薬が多い一方、複数の有効成分を組み合わせた薬もあります。
病気の原因を特定し、それに直接作用する成分を用いることで、高い治療効果を得ることを目的としています。
例えば細菌感染には抗生物質、炎症には抗炎症薬を使用するなど、特定の病原体にピンポイントで働きかけるのが特徴です。
そのため、症状の改善が早く、即効性があるというメリットがあります。
しかし、その分副作用のリスクがある点には注意が必要です。
特定の成分が強く作用するため、過剰摂取や長期使用によって副作用が出ることもあります。
また西洋医学では病名に基づいて薬が処方されるため、同じ病名の患者には基本的に同じ薬が処方されることが多いです。
一方で、体質や症状の個人差が考慮されにくいこともあるため、患者さんによっては薬の効果に差が出ることもあります。
| 漢方薬は漢方医学に基づいて処方される薬
漢方薬は、いくつかの生薬を組み合わせた処方であり、それぞれの生薬に含まれる成分が相互に作用して、体のバランスを整えることを目的としています。
漢方医学では病気は体内のバランスの乱れによって引き起こされると考えられています。
そのため漢方薬は特定の症状を抑えるだけでなく、体全体の調子を整え、自然治癒力を高めることを目的としているのが特徴です。
処方には、患者の体質や症状(証)を重視し、同じ病気でも異なる漢方薬が選ばれることが一般的です。
漢方薬は植物や鉱物などの天然由来の生薬を複数組み合わせて作られます。
そのため一般的に作用が穏やかで、副作用が少ないといわれています。
ただし即効性に欠けることが多く、効果を実感するにはある程度継続して服用し続けなくてはいけません。
また漢方薬は漢方医学における基本的な概念である『気・血・水』のバランスを考慮して処方されます。
| 西洋薬と漢方薬のそれぞれ向いている病気

西洋薬と漢方薬はそれぞれ向いている病気が異なります。
・漢方薬:原因が特定できていない病気や体質が関係している病気など
ここでは上記についてそれぞれ解説します。
| 西洋薬の向いている病気
西洋薬は原因が特定できている病気に適しています。
ガイドラインに基づいて処方されるのが一般的で、例えば細菌感染症の治療では抗生物質が処方され、インフルエンザなどのウイルス感染症では抗ウイルス薬が処方されます。
漢方薬とは異なり、体質を考えずに病名や症状のみで判断して治療を行うのが特徴です。
その病気に適した治療薬が確立されている場合は、西洋薬のほうが即効性が期待できます。
| 漢方薬の向いている病気
漢方薬は原因が特定できていない病気や体質が関係している病気に適しています。
例えば、検査で異常が見られない場合でも自覚症状が続くときには、体全体のバランスを整える漢方薬が適しています。
さらに以下のようなケースも漢方薬の処方が向いているでしょう。
・体質改善が必要な病気
・心身症傾向の強い病気
・高齢者・体力低下傾向の著しいもの
漢方薬は西洋薬とは異なり、病名診断にこだわらず、患者さんの証(体質・体力・症状の現れ方などの状態)に基づいて処方されます。
具体的には月経に伴う不調や、更年期障害、冷え性、抑うつ、肥満、アレルギー疾患といったさまざまな症状や病気において漢方薬が処方されるケースがあります。
このほかにも、慢性頭痛やしびれ、疼痛、めまいなどの症状にも漢方治療が効果的です。
また近年では抗がん剤の副作用軽減を目指す目的で、漢方薬が処方されることもあります。
| 西洋薬と漢方薬どちらを選ぶべき?

西洋薬と漢方薬それぞれのメリット・デメリット・適しているケースを簡単にまとめると以下の通りです。
| 西洋薬 | 漢方薬 | |
| メリット | 即効性がある
高い治療効果がある 薬の効果が化学的に証明されている |
病気の根本的な原因にアプローチできる
副作用が比較的少ない 初期症状の改善により病気の重症化を予防できる |
| デメリット | 副作用のリスクがある
根本的な原因解決ができない場合が多い 長期服用による依存性や薬剤耐性の問題がある |
即効性が低いため、効果が現れるまで時間がかかることがある
効果には個人差がある |
| 適しているケース | 症状の原因が特定できているケース
即効性が求められるケース |
慢性的な症状に悩んでいるケース
体質改善を目的とするケース |
ここでは上記についてそれぞれ詳しく解説します。
| 西洋薬のメリット・デメリット・適しているケース
西洋薬は現代医学の進歩によって開発され、多くの病気の治療に用いられています。
特定の症状や病原体に対して即効性があり、病気の進行を抑える力が強いのが特徴です。
しかしその一方で副作用のリスクや長期間の使用に伴う問題も指摘されています。
ここでは西洋薬のメリット・デメリット・適しているケースを見てみましょう。
– 西洋薬のメリット
西洋薬の最大のメリットは、即効性と高い治療効果です。
科学的な研究に基づいて開発されており、特定の病気や症状に対してピンポイントで作用するため、短期間で効果を発揮するものが多くあります。
例えば抗生物質は細菌感染症を短期間で治療し、解熱鎮痛剤は発熱や痛みを素早く緩和します。
また病気の進行を抑えたり、重症化を防ぐのにも有効です。
高血圧や糖尿病などの慢性疾患では、薬を服用することで病状をコントロールし、合併症のリスクを減らすことができます。
さらに薬の効果が化学的に証明されているため、医師の診断に基づいて適切に使用することで、安全かつ効果的な治療が可能になります。
特定の病気に対して確立された治療法が存在するため、治療計画が立てやすいのもメリットの一つです。
– 西洋薬のデメリット
西洋薬のデメリットとして、副作用のリスクがあることが挙げられます。
薬が特定の症状を抑える一方で、体の他の部分にも影響を与えることがあるのです。
また対症療法が中心で、根本的な原因の解決には至らないことが多いのもデメリットの一つです。
例えば痛み止めや解熱剤は症状を一時的に抑えることはできますが、痛みの原因そのものを解消するわけではありません。
さらに長期間の使用による依存性や耐性の問題もあります。
一部の薬には、長く使うことで効果が弱まる『薬剤耐性』が生じるものがあり、抗生物質の乱用による耐性菌の増加が問題視されています。
また精神安定剤や睡眠薬などは依存性が強く、自己判断での長期使用には注意が必要です。
– 西洋薬が適しているケースト
西洋薬は、症状の原因が特定できている場合や即効性が求められる場合に適しています。
具体的にはインフルエンザなどの急性疾患、頭痛や関節炎などの強い痛み、心筋梗塞やアナフィラキシーショックをはじめとする救急医療が必要なケースなどです。
上記のようなケースではすぐに症状を緩和させる必要があるため、漢方薬よりも西洋薬のほうが適しています。
| 漢方薬のメリット・デメリット・適しているケース
漢方薬は自然由来の生薬を組み合わせることで、体全体のバランスを整え、病気の根本的な原因にアプローチするのが特徴です。
しかしその一方で即効性が低いことや、体質によって効果が異なるなどのデメリットもあります。
ここでは漢方薬のメリット・デメリット・適しているケースを見てみましょう。
– 漢方薬のメリット
漢方薬の最大のメリットは、体質改善を目的とし、病気の根本的な原因にアプローチできることです。
西洋薬が特定の症状を抑えることに重点を置くのに対し、漢方薬は体のバランスを整え、自然治癒力を高めることで病気になりにくい体を作ることを目的としています。
そのため、慢性的な不調や体質の悩みに対して有効とされています。
また副作用が比較的少ない点もメリットの一つです。
漢方薬は自然由来の生薬を使用しているため、西洋薬のような強い化学成分による副作用のリスクが低く、長期間の服用にも適しています。
ただし個人の体質や生薬の組み合わせによっては体に合わない場合もあるため、医師のアドバイスを受けることが大切です。
さらに病気の予防や未病の緩和にも有効です。
未病とは、まだ病気として診断されていないが、健康状態が悪化しつつある段階を指します。
漢方ではまだ病気として診断されない『未病』の段階から治療を行えるという特徴があるのです。
例えば冷え性や疲れやすい体質、ストレスによる不調など、西洋医学では診断が難しい状態でも、漢方薬を取り入れることで健康維持につながることがあります。
– 漢方薬のデメリット
漢方薬には即効性が低いというデメリットがあります。
西洋薬のように症状をすぐに抑えるのではなく、体質を根本から改善することを目的としているため、効果が現れるまでに時間がかかることが多いです。
特に慢性的な症状や体質改善を目的とした場合は、数週間から数ヶ月の服用が必要になることもあります。
また体質によって効果に個人差があることもデメリットの一つです。
漢方薬は『気・血・水』のバランスや『実証・虚証』といった体質に基づいて処方されるため、同じ症状でも人によって適した漢方薬が異なります。
誤った処方をすると効果が得られないだけでなく副作用が現れることもあるため、医師の指導のもとで適切な薬を選ぶことが大切です。
– 漢方薬が適しているケース
漢方薬は慢性的な症状や体質改善を目的とする場合に適しています。
例えば冷え性や疲労感といった慢性的な体調不良、不眠やイライラなどの自律神経の乱れからくる不調、月経不順や更年期障害などの女性特有の悩みなどに有効です。
このほかにも、体質そのものの改善により症状が良くなる場合は、漢方薬の服用が推奨されます。
| 西洋薬と漢方薬は併用できる?

漢方薬と西洋薬はそれぞれ異なる特徴を持っていますが、適切な方法で併用することで相乗効果を得ることができます。
西洋薬は特定の病気や症状に直接作用し、効果を発揮することが特徴です。
一方、漢方薬は体質改善や自然治癒力の向上を目的とし、体全体のバランスを整えることで根本的な治療を目指します。
これらを組み合わせることで、急性症状を抑えながら長期的な健康維持を図ることが可能です。
例えば高血圧や糖尿病などの慢性疾患では、西洋薬で症状をコントロールしつつ、漢方薬で体質改善を図るケースがあります。
また、抗がん剤治療による副作用を軽減するために漢方薬が用いられることもあるのです。
実際に日本の医療現場では漢方薬と西洋薬の併用が行われており、研究によってその有効性が報告されています。
(参照:「和漢薬と西洋薬の併用における適正使用に向けた臨床薬理学的研究」慶応義塾大学学術情報リポジトリ)
ただし中には併用禁忌とされる薬もあるため注意が必要です。
漢方薬と西洋薬の併用を検討する際は、必ず医師に相談しましょう。
| まとめ
西洋薬は特定の病気や症状に対してピンポイントに作用する薬で、漢方薬は慢性的な症状や体質改善を目的とした薬です。
例えば冷え性や疲労感、イライラ、月経不順、更年期障害などの慢性的な症状に悩まされている場合、西洋薬よりも漢方薬が適しているケースがあります。
西洋薬と漢方薬どちらが自分に適しているかわからないという方は、一度医療機関を受診して医師に相談してみるとよいでしょう。
当院では、オンライン診療による医療用漢方の処方に対応しています。
慢性的な症状にお悩みの方や自宅にいながら体質改善を目指したい方は、ぜひご相談ください。